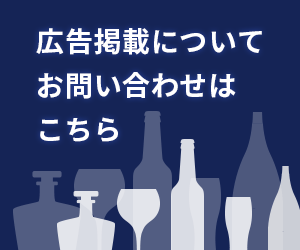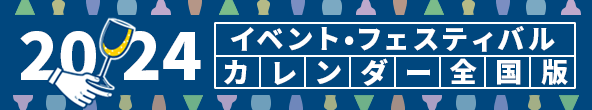山形の日本酒を厳選! ゼッタイ飲んでみてほしい「吟醸王国」のおすすめ銘柄を紹介

山形は日本酒造りが盛んな土地で、「全国新酒鑑評会」の金賞受賞数が第1位になるなど高レベルなお酒が数多く造り出されています。今回は「吟醸王国」とも称される山形の日本酒の特色や味わいの特徴などに加え、山形を代表する日本酒9銘柄を厳選して紹介します。
- 更新日:
まずは山形の日本酒の特色をみていきましょう。
山形の日本酒の特色は? 味わいの特徴も紹介

kitsune05 / Shutterstock.com
はじめに、山形の日本酒の概要をみていきます。
山形は「吟醸王国」!「令和4酒造年度全国新酒鑑評会」では金賞受賞数全国1位に
山形には昔からたくさんの日本酒蔵元があり、これまでに「十四代(じゅうよんだい)」「出羽桜(でわざくら)」「くどき上手(じょうず)」「東光(とうこう)」「上喜元(じょうきげん)」「初孫(はつまご)」など、数多くの有名銘柄を輩出してきました。
以前から各蔵元が力を結集して研究を行うなど、地域を挙げて切磋琢磨してきた歴史もあるため、山形の日本酒造りはハイレベル。「令和4(2022)酒造年度全国新酒鑑評会」では、金賞受賞数が都道府県別で第1位に輝くなど、「吟醸王国やまがた」の名のとおり、技術力の高さに裏打ちされたおいしいお酒を世に送り出しています。
さらに、付加価値の高い特定名称酒の高価格商品だけでなく、地元の人々に愛されている手ごろな価格帯のお酒もないがしろにせず、大事に育んできているのも山形の特徴といえるでしょう。

ganzosr400 / PIXTA(ピクスタ)
「出羽燦々(でわさんさん)」など良質な山形オリジナル酒米を次々と開発
山形の日本酒の酒質向上に好影響を与えているといわれているのが、蔵元、農業関係者、行政が一体となって取り組む山形オリジナル酒造好適米の開発です。
平成7年(1995年)に誕生した酒造好適米「出羽燦々」は、おもに純米吟醸酒に使われているお米。その後の平成17年(2005年)には純米酒向きとされる「出羽の里」、平成27年(2015年)には純米大吟醸酒、大吟醸酒向けと位置づけられた山形産酒造好適米のフラッグシップ「雪女神(ゆきめがみ)」が生まれています。
山形では、精米歩合55パーセント以下の「出羽燦々」のみを原料米とし、同じく山形オリジナルの「山形酵母」と麹菌「オリーゼ山形」で醸した純米吟醸酒のうちの、厳正な審査会を通過したものを、各蔵元共通のブランド日本酒「DEWA33(でわさんさん)」に認定しています。
また「山形讃香(やまがたさんが)」という、世界に誇れる高級な日本酒をめざし、山形県と山形県酒造組合が共同で開発した純米大吟醸酒ブランドもあります。現在の「山形讃香」は、選りすぐられた優良な「雪女神」を精米歩合35パーセントで使用し、その年に選ばれた優秀蔵元が醸造を担当して造る、すべてが山形産の至極の1本となっています。
どちらも見かけたら、ぜひ試してみてください。「やわらかくて、巾がある」と評判の「DEWA33」には、山形の日本酒に対する誇りと責任の証しともいえる「純正山形酒審査会認定証」が貼られています。

rara / PIXTA(ピクスタ)
地理的表示(GI)「山形」にも指定
山形県は、日本酒造りに適した気候や風土、水にも恵まれた地。県内には51もの蔵元が点在し、官民・地域一体となって人材育成や醸造技術の向上に取り組んできました。
そして平成28年(2016年)12月、山形県は国税庁長官より酒類(清酒)の地理的表示(GI)「山形」の指定を受けました。1つの県に対するGIの指定は初めてのことです。
酒類の地理的表示(GI)制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。産地ならではの特性が確立されていることが条件となっていて、産地からの申し立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができます。
GI「山形」の使用に際しては、以下の事項を満たしている必要があります。
出典 国税庁|酒類の表示 別紙1 地理的表示「山形」生産基準(1)原料
◇米及び米こうじに国内産米のみを用いたものであること。
◇水に山形県内で採水した水のみを用いたものであること。
◇酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の原料を用いたものであること。
ただし、酒税法施行令第2条に規定する清酒の原料のうち、アルコール(原料中、アルコールの重量が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えない量で用いる場合に限る。)以外は用いることができないものとする。
(2)製法
◇酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の製造方法により、山形県内において製造されたものであること。
◇製造工程上、貯蔵する場合は山形県内で行うこと。
◇山形県内で、消費者に引き渡すことを予定した容器に詰めること。
GIの指定も受けた山形のお酒は、総じてやわらかく、透明感のある酒質といえます。
一方で、当たり前のことですが、蔵元ごとに仕込み水もこだわりも杜氏も異なるため、できあがる日本酒の個性はまさに百花繚乱。吟醸酒の特長でもあるフルーティーな味わいのものをはじめ、辛口の味わいや生酛(きもと)造りにこだわったしっかりとした味わいを特長とする銘柄もあるなど、山形はさまざまな味わいの日本酒がたのしめる土地でもあるのです。
山形の日本酒|フルーティーなおすすめ銘柄3選
「吟醸王国」の名にふさわしい、フルーティーな味わいが特徴の3銘柄を紹介します。
「十四代(じゅうよんだい)」高木酒造|山形の日本酒を代表する大人気銘柄

NOBUHIRO ASADA / Shutterstock.com
高木酒造が手掛ける「十四代」は、芳醇旨口ブームの火つけ役となった銘柄で、原料米に由来する香りと甘味が存分に感じられる、みずみずしい味わいが特長。入手困難な「幻の酒」としても知られています。
代表酒としては、清らかな果実味を感じさせる特別本醸造酒「十四代 本丸(ほんまる)」、フレッシュかつ品のよい香りと優しい甘味が特長の大吟醸酒「十四代 双虹(そうこう)」、斗瓶囲いを氷温熟成させた限定品で甘味、旨味があり、余韻もたのしめる純米大吟醸酒「十四代 龍月(りゅうげつ)」などが挙げられます。
高木酒造は400年以上の歴史を持つ老舗蔵元。地元の人々に愛されてきた「朝日鷹(あさひたか)」という銘柄も造り続けています。
製造元:高木酒造株式会社
公式サイトはありません
「出羽桜(でわざくら)」出羽桜酒造|吟醸酒ブームを切り拓いた銘酒

画像提供:出羽桜酒造株式会社
「出羽桜」は、江戸時代から酒造りを続ける天童市の蔵元、出羽桜酒造の看板銘柄です。
出羽桜酒造がめざしている日本酒は、プロではない一般の愛飲家にも違いが伝わるような、わかりやすい酒質のお酒。吟醸酒だけでなく、普通酒のレベル向上も図っています。
「出羽桜」の代表酒といえば、昭和55年(1980年)の発売以来のロングセラー定番酒で吟醸ブームの先駆けとなった「出羽桜 桜花(おうか)吟醸酒」。フルーティーでさわやかな「桜花」の酒質は、多くの人々の支持を受けています。
「出羽桜」は輸出にも力を入れていて、きれいな香りと繊細で優雅な味わいの「出羽桜 大吟醸酒」や、果実を想わせる香りとスムーズな飲み口の純米大吟醸酒「出羽桜 一路」などが、海外でも高く評価されています。
製造元:出羽桜酒造株式会社
公式サイトはこちら
「秀鳳(しゅうほう)」秀鳳酒造場|原料から引き出された香りと旨味がたのしめる

出典:有限会社秀鳳酒造場サイト
山形市の秀鳳酒造場は、米・水・麹・酵母といった原材料から香りと旨味を引き出す酒造りに定評のある蔵元。精米機を導入し自社精米を行うなど、質の高い日本酒を造るための設備投資も積極的に行っています。
秀鳳酒造場の代表銘柄「秀鳳」は、香り高く深い味わいの日本酒です。
なかでも「秀鳳 純米大吟醸 出羽燦々33」は、山形生まれの酒造好適米「出羽燦々」を、名前にちなみ精米歩合33パーセントまで磨いて使用したもので、フルーツのような香りが堪能できます。
また、もともとは山形の農業高校で交配されたという酒造好適米「玉苗(たまなえ)」を使用した「秀鳳 純米大吟醸 玉苗」は、バナナを想起させる甘く華やかな香りと、さらりとした口当たりの原酒。メロンのようなフルーティーな味わいや、パイナップルジュースのような甘味も感じさせるもので、「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2018」では大吟醸部門の最高金賞に輝いています。
製造元:有限会社秀鳳酒造場
公式サイトはこちら
山形の日本酒|辛口のおすすめ銘柄3選
日本酒ファンの支持が高い辛口酒がラインナップされている山形の3銘柄を紹介します。
「ばくれん」亀の井酒造|大人気の超辛口美酒

kathayut kongmanee / Shutterstock.com
鶴岡市の亀の井酒造は、「くどき上手」という銘柄で知られる全量吟醸酒の蔵元です。
今回紹介する、大人気の超辛口酒「ばくれん」は、「くどき上手 辛口純吟」の開発過程で生まれたといわれています。
精米歩合55パーセントの「美山錦」を使用した、あずき色ラベルの「ばくれん 超辛口吟醸」は、「赤ばくれん」とも呼ばれる定番酒。品のよいほのかな吟醸香と、軽快でまろやか、すっきりキレのよい味わいが特長で、超辛口のお酒でありながら飲みやすく杯が進みます。
このほか、毎年2月ごろに発売される黒いラベルの「黒ばくれん 超辛口吟醸 生酒」や、毎年10月ごろに発売される「白ばくれん 超辛口吟醸」などの限定流通商品も「ばくれん」シリーズにラインナップされています。
「黒ばくれん」は原料米に「亀の尾4号」を使った濃醇な旨味も感じさせる生酒、酒米の王様「山田錦」の母親にあたる「山田穂」という米を使った「白ばくれん」は米の旨味も感じさせる生詰め酒です。
さらに近年では、「赤ばくれん」の姉妹品と位置づけられた「新・ばくれん」シリーズも登場するなど、ラインナップの充実度も高まってきています。
製造元:亀の井酒造株式会社
公式サイトはありません
「楯野川(たてのかわ)」楯の川酒造|全量純米大吟醸蔵の矜持が伝わる辛口酒

出典:楯の川酒造株式会社サイト
「楯野川」は、江戸時代から酒造りを行う酒田市の蔵元、楯の川酒造の主要銘柄です。
楯の川酒造で造られている日本酒は、すべて純米大吟醸酒。品質を追求した酒造りから多くの良酒を生み出し、地元山形にとどまらず、全国そして海外にもファン層を広めています。
原料米を精米歩合1パーセントまで磨いて醸した「純米大吟醸 光明(こうみょう)」シリーズをはじめ、原材料にこだわり抜き、酒造技術の粋を集めて造り上げるハイクラス商品が話題となる一方、完全手造りで食中酒として醸される「Basic(ベーシック)シリーズ」のラインナップも良酒ぞろい。
なかでも「純米大吟醸 本流辛口」は、数多ある淡麗辛口のお酒とは違い、原料米「出羽燦々」の旨味がしっかりと感じられる、芳醇辛口の純米大吟醸酒。穏やかな香りの先に辛味と旨味を感じさせる、キレもさわやかで心地のよい1本です。
「Basicシリーズ」にはほかにも軽くソフトな口当たりの「純米大吟醸 清流」や、特別栽培の「美山錦」を使った、旨味と酸味のバランスが抜群の食中酒「純米大吟醸 美しき渓流」などがラインナップされています。
製造元:楯の川酒造株式会社
公式サイトはこちら
「山形正宗(やまがたまさむね)」水戸部酒造|「銘刀の切れ味」ともいわれるシャープな味わい

出典:株式会社水戸部酒造サイト
「山形正宗」は、天童市の蔵元、水戸部酒造の主要銘柄です。
水戸部酒造が手掛ける日本酒は、すべて純米酒。農業法人を設立し、原料米の自家栽培も行っています。
また、水戸部酒造の仕込み水は、山寺(やまでら)を源流とする天然水。ミネラル分を多く含んでいるため、「銘刀の切れ味」とも称されるシャープで硬質な「山形正宗」の飲み口を生み出します。
「山形正宗」の代表酒として挙げられるのが、原料米由来の豊かな旨味とシャープな後味が特長の「山形正宗 辛口純米」。「出羽燦々」を60パーセントまで磨き、ていねいに醸したロングセラー商品です。
そのほか、自社産の米を使った純米吟醸酒「山形正宗 稲造(いなぞう)」、蔵元が輸入している「タナラ社」の生ハムに合う日本酒を造ろうと、ワインの発酵技術を転用して造った「山形正宗 まろら」など、「山形正宗」は王道の定番酒からチャレンジングなお酒までたのしめる銘柄です。
製造元:株式会社水戸部酒造
公式サイトはこちら
山形の日本酒|全国新酒鑑評会常連蔵元のおすすめ銘柄3選
酒造技術を評価する全国新酒鑑評会の常連で、長年にわたり高評価を受けている3蔵元の主要銘柄を紹介します。
「東光(とうこう)」小嶋総本店|上質な手造りの酒

出典:株式会社小嶋総本店オンラインストア
米沢市の小嶋総本店は、つねに第一級の品質をめざし、しっかり手をかけた手造りの酒造りを行ってきた安土桃山時代創業の蔵元。「東光」はその主要銘柄です。
代表酒としてまず挙げられるのは「東光 純米大吟醸袋吊り」。吊った酒袋からしたたり落ちる雫だけを集めたもので、香り高く、味わいは緻密かつ妖艶、フルーティーで滑らかな飲み口も印象的な逸品です。
そのほか、フルーティーな香りと透明感のある質感が特長の「東光 純米大吟醸 雪女神」や、優しい果実様の香りとやわらかで繊細な口当たりが魅力的な「東光 純米吟醸 出羽燦々」など、地元山形生まれの酒造好適米を使った商品も存在感を放っています。
製造元:株式会社小嶋総本店
公式サイトはこちら
「上喜元(じょうきげん)」酒田酒造|酒田の名蔵が醸す銘酒

sarakazu / PIXTA(ピクスタ)
「上喜元」の醸造元、酒田市の酒田酒造は、5つの蔵元が合併してできた蔵元で、純米酒、純米吟醸酒の製造研究に力を入れてきました。
生酛(きもと)造りと吟醸造りにこだわり、さまざまな酵母や米を使った酒造りが行われていて、コクとキレのある深い味わいが特長の日本酒「上喜元」を造り続けています。
なかでも「上喜元 純米吟醸 亀の尾」は、米の旨味をたっぷりと感じさせる逸品。このほか、やわらかな香りとふくよかな旨味が特長の「上喜元 純米 出羽の里」や、時には鑑評会出品酒を含む大吟醸をブレンドすることもあるという、地元で大人気の季節限定酒「上喜元 翁(おきな) 生詰」など、「上喜元」ブランドにはバラエティーに富んだ旨い酒が数多くラインナップされています。
製造元:酒田酒造株式会社
公式サイトはありません
「初孫(はつまご)」東北銘醸|生酛造りにこだわった深みのある味わい

出典:東北銘醸株式会社サイト
「初孫」は酒田市の蔵元、東北銘醸の主要銘柄です。
東北銘醸が手掛けるお酒は、すべて生酛造りで醸されます。品質にこだわり、空気中の乳酸菌を活用して造られる東北銘醸の日本酒は、生酛ならではの力強くしっかりとした酒質、そして深みのある味わいとすっきりした後口を特長としています。
「初孫」ブランドの代表酒といえば「大吟醸」。「山田錦」を自家精米で丹念に40パーセントまで磨き上げ、伝承の手造りの技が息づく生酛造りで醸したもので、品のよい吟醸香と芳醇な味わいが堪能できます。
華麗な香りと重厚感漂う優雅な味わいをたのしむなら「純米大吟醸 祥瑞(しょうずい)」、料理と合わせるなら、滑らかな口当たりと心地のよい酸味、ふっくらとした優しい旨味ときれいな後味が特長の「出羽の里 純米酒」もおすすめです。
製造元:東北銘醸株式会社
公式サイトはこちら
蔵元のお酒を毎週1つずつ飲んでみたくなるほど個性が豊かでいずれも旨い山形の日本酒。おいしいので飲みすぎには注意ですが、気になったものから少しずつ試して、たくさんのお気に入りをみつけてくださいね。