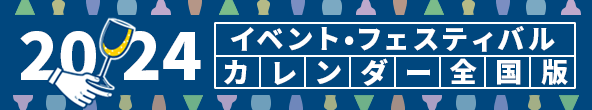日本酒の造り方は複雑? 醸造の工程をわかりやすく紹介【日本酒の基礎知識】

日本酒は単純な造り方(作り方)でできあがるわけではなく、数多くの工程を経て醸造されます。今回は、精米、洗米・浸漬、蒸米・放冷、麹造り、酒母造り、醪造り、上槽、ろ過、火入れ、貯蔵・調合・割水、瓶詰めなど、それぞれに意味のある製造工程 を順番に紹介します。
- 更新日:
日本酒の製造工程を、流れに沿ってみていきましょう。
日本酒の製造方法を工程ごとに紹介

shige hattori / PIXTA(ピクスタ)
日本酒の造り方を、精米から順番に紹介していきます。
精米
米を原料とする日本酒。その造り方の第1歩目となる工程が、玄米を削って白米にする「精米」です。
玄米の外側部分には、雑味のもととなるタンパク質や脂質などが多く含まれています。日本酒造りの精米は、これらの成分を取り除く目的で行われます。
日本酒のラベル表示にある「精米歩合」とは、精米後に残った米の割合をパーセントで表したものです。
普段ごはんとして食べている米の精米歩合は92パーセント前後が主流ですが、日本酒の原料米の精米歩合は70パーセント以下がほとんど。雑味が少ないものが多い大吟醸酒は規定が50パーセント以下、なかには精米歩合30パーセント台のお酒もみられます。
実際の精米にはおもに竪型(たてがた)精米機が使われます。機械化されているからといって短時間で済むわけではなく、一般的に、玄米600キログラム(10俵分)を精米歩合70パーセントにするにはおよそ10時間、50パーセントまで削るにはおよそ50時間かかるといわれています。
長時間精米を行ったあとの米は摩擦熱を帯びています。そのままでは米が割れたり吸水し過ぎたりするため、冷暗所で2~3週間保管して米の状態を安定させる「枯らし」を経てから次の工程に移ります。

freeangle / PIXTA(ピクスタ)
洗米・浸漬(しんせき)
次に行われるのは、米を洗う「洗米」です。食用の米と同じく、米の糠(ぬか)や米くずを洗い流す目的で行われます。精米後の米は割れやすく、水も吸いやすいことから、洗米には細心の注意と手早さが必要になります。
洗米には多くの場合、自動洗米機が用いられますが、大吟醸酒などで使われるよく削られた米については、手作業で行われることもあります。
洗米後はすぐに、新しい水に米を浸けて水分を吸収させる「浸漬」が行われます。
浸漬は、酒質を決める要素のひとつ、蒸し米のよしあしを左右する大切な工程。内側が軟らかく外側が硬い理想的(外硬内軟)な蒸し米を造るためには、米に適量の水分を吸収させる必要があるのです。
浸漬時間は米の種類や精米歩合、その日の気温などさまざまな条件によって決まります。洗米時から時間管理が行われ、よく削られた米などでは秒単位の計測をしながらごく短い時間、浸漬させる「限定吸水」が行われ、過剰な吸水を防ぎます。
なお浸漬後の米は、表面の水分を取ってなかの水分を均一にするため、一晩程度「水切り」されます。

Sunrising / PIXTA(ピクスタ)
蒸米(じょうまい/蒸し)・放冷
水切りが済んだ米は、「甑(こしき)」と呼ばれる大きな蒸し器や自動連続蒸米機を使って蒸されます。この工程は「蒸米」あるいは「蒸し」、蒸し上がった米は「蒸し米」と呼ばれます。
蒸米の目的は、高温の蒸気で加熱して米のデンプンをα化(軟らかく粘り気のある状態になること。糊化)させること。α化により結晶状のデンプンに隙間ができるため、麹(こうじ)菌が作り出す酵素の作用が受けやすくなり、アルコール発酵時に必要な糖への変化もスムーズになるのです。
また、100度の蒸気でじっくり加熱された米は、ほぐれやすく外側が硬く内側が軟らかい「外硬内軟(がいこうないなん)」の状態になりやすいといわれています。外硬内軟の蒸し米は麹菌が繁殖しやすいという特徴があります。
蒸し上がった米は麹用、醪(もろみ)造りの際の掛米(かけまい)用、酒母(しゅぼ)用に分けられ、それぞれの適温まで冷まされます。
この「放冷」の工程には、むしろ(筵)の上に広げる昔ながらの冷却方法や、ベルトコンベアで移動させながらファンで冷やす方法などがあります。

unterwegs / Shutterstock.com
麹(こうじ)造り(製麹)
蒸米の放冷後は、日本酒の造り方のなかで最重要とされる「麹造り」の工程に進みます。麹造りは「製麹(せいきく/せいぎく)」とも呼ばれ、手作業や製麹機で行われます。
「麹」とは麹菌の胞子を蒸し米に繁殖させたもので、米のデンブン質を糖化させる酵素を酒母や醪(もろみ)に供給する・酵母の栄養になる・麹に由来する香味成分の生成といった役割があります。
昔から「一麹、二酛(もと)、三造り」といわれるように、麹のできあがりは日本酒の品質に大きな影響を与えます。
麹は麹室(こうじむろ)、または製麹室と呼ばれる専用の作業部屋で蒸し米に麹菌の胞子を振りかけ、何度もかき混ぜて造られます。できあがりまでには2日間ほどかかるとされています。

Jason Adamson / Shutterstock.com
酒母(しゅぼ)造り
麹ができあがったら「酒母造り」に移行します。
「酒母(酛〈もと〉)」とは、アルコール発酵を行う微生物の酵母を大量に増殖させたもの。材料は蒸し米・麹・仕込み水・酵母で、たくさんの米をスムーズに発酵させる目的で造られます。
アルコールを生み出す酵母は、雑菌に弱く酸性に強いという特徴があります。一方、総じて雑菌は酸性の環境では生きられないため、おもに乳酸を使って酒母を酸性にします。
酒母には、醸造用乳酸を添加して造る「速醸酛(そくじょうもと)」、自然界の乳酸菌を取り込んで乳酸を生成させる昔ながらの「生酛(きもと)」、生酛を造る工程のうち、蒸し米と麹をすりつぶす「山卸し(やまおろし/酛すり)」を廃した「山卸廃止酛(山廃酛・やまはいもと)」などがあります。
完成まで、速醸酛は10日から2週間、生酛系とされる生酛や山廃酛は3週間から1カ月程度かかります。
現在は管理しやすく比較的短い時間で完成する速醸酛が主流です。生酛系は手間と時間がかかり管理も難しいことから一時期衰退しましたが、濃醇な酒質になる傾向があり、近年では見直されつつあります。

Cybister / PIXTA(ピクスタ)
醪(もろみ)造り(仕込み)
酒母造りを終えたら、日本酒造りのクライマックスともいえる「醪造り(仕込み)」に入ります。
醪造りの目的は本格的なアルコール発酵を行うこと。方法はいくつかありますが、一般的な三段仕込みは4日間、3回に分けて行われます。仕込みを小分けにする理由は、雑菌が繁殖するリスクを抑えるためです。
1日目は醪全体の7パーセントほどになる酒母と、15~20パーセントほどの原料(蒸し米・麹・仕込み水)をタンクに入れて櫂(かい)でかき混ぜます。これを「初添え(添え仕込み)」といいます。2日目は「踊り」といい、何も入れず酵母の増殖を待ちます。
3日目の「仲添え(仲仕込み)」では醪全体の30パーセント程度の原料を、4日目の「留添え(留仕込み)」では残りすべての原料を投入します。
アルコール発酵は留添えの日から2~5週間ほどかけて進みます。発酵中は熱が生じるため、杜氏の指示により適切な温度管理が行われます。
なお、日本酒の発酵方法は、麹による米のデンプン質の糖化と、その糖を酵母が食べることで起こるアルコール発酵が同一タンク内で並行して行われるもので、「並行複発酵」と呼ばれています。

カージ / PIXTA(ピクスタ)
上槽(じょうそう)
「上槽」は、アルコール発酵が終わった醪を搾って酒粕と液体に分ける工程です。
上槽の手法はいくつかあり、自動圧搾機で行われるのが一般的です。
伝統的な手法としては、醪を入れた酒袋(さかぶくろ)を「槽(ふね)」という器具のなかに敷き詰め、上から圧力をかけて搾る「槽搾り(ふなしぼり)」があります。
また、全国新酒鑑評会出品用の大吟醸酒や高級酒などでは、醪を入れた酒袋をぶら下げて自然に滴り落ちる酒を集める「袋吊り(袋搾り/雫〈しずく〉搾り)」が行われることもあります。
袋吊りで上槽した日本酒は、滴り落ちるお酒を指して「雫酒(しずくざけ)」と呼ばれたり、一斗瓶に採集するため「斗瓶囲い(とびんがこい)」と呼ばれたりします。
上槽が終わった直後の日本酒は、「おり(澱/滓)」と呼ばれる細かな米粒などの固形物が浮いているため、タンクのなかにしばらく置いてそれらを沈殿させ、上澄み部分を抽出する「おり引き」を行います。

freeangle / PIXTA(ピクスタ)
ろ過(濾過)
おり引き後には、お酒のなかに残っている細かな固形物や酵母の除去をおもな目的とする「ろ過(濾過)」が行われます。ろ過機のフィルターを通す方法や、粉末状の活性炭を使用する方法があります。
なお、ろ過はこのタイミングのほか、割水のあとに脱色や香味の調整をおもな目的として行われることもあります。
また、ろ過を行わない「無ろ過(無濾過)」の日本酒も販売されています。無ろ過の日本酒の見た目は淡い白色から黄白色で、多様な香りの成分が残っているのが特徴です。
ろ過の表示については法的な規定がないことから、ろ過機、活性炭とも使わないもののほか、活性炭を使わずろ過機のみを用いたものを「無ろ過」としている場合もあります。

kazoka / Shutterstock.com
火入れ
「火入れ」の工程では、60~65度ほどの温度で10分程度加熱する「低温加熱殺菌」が行われます。
その目的は、味わいを甘く変化させる糖化酵素の働きを止めことと、お酒の色味や香味に異常をもたらす「火落ち菌」などを殺菌すること。一般的な日本酒では、貯蔵前のこのタイミングと瓶詰め前の2回行われます。
一方で、フレッシュな味わいを残すため、火入れを行わなかったり、火入れの回数を減らしたりしている日本酒もあります。
火入れをまったく行わないのは「生酒(なまざけ)」、貯蔵前に1回だけ行うのは「生詰め酒」、瓶詰め前のタイミングで1回だけ行うのは「生貯蔵酒(なまちょぞうしゅ)」と呼ばれています。
火入れの方法は複数あります。なかでも、お酒が通る管をタンク内のお湯にくぐらせる「蛇管(じゃかん)式」という方法が広く行われています。

αR / PIXTA(ピクスタ)
貯蔵・調合・割水(割り水)
火入れ後の日本酒は、通常一定期間タンクで「貯蔵」されます。貯蔵時の理想の温度は15度前後またはそれ以下。熟成させることで酒質が落ち着き、まろやかな味わいになるといわれています。
また近年では、後述の「割水」を先に行って、お酒を瓶に詰めてから冷蔵庫で貯蔵を行う「瓶囲い」を行う蔵元も増えてきています。
タンクでの貯蔵期間を終えると「調合」が行われます。貯蔵されたお酒はタンクごとに酒質が異なるため、蔵人がテイスティングのうえで各タンクのお酒をブレンドして酒質を一定化させます。
次に行われるのが、アルコール度数と香味のバランスを調整する「割水(割り水)」です。割水前の「原酒」は18度以上のアルコール度数のものもあるため、仕込み水を加えて15~16度になるように調整されます。この工程は「加水」ともいわれます。
加水する前後に、透明度を高めるための脱色や香味の調整のための2回目のろ過を行う場合もあります。
なお、調合・2回目のろ過・加水をまとめて「調合精製」と呼ぶこともあるようです。

Tomoaki Umino / PIXTA(ピクスタ)
瓶詰め
いよいよ出荷前の「瓶詰め」です。瓶詰めは、ほぼ機械化されている工程。しっかりとした衛生管理のもとで行われ、品質チェックを経てから出荷されるのが一般的です。
瓶詰めの前には、2回目の火入れや生貯蔵酒の火入れが行われます。
また、瓶詰め後に火入れが行われる場合もあります。代表的なものに、「パストライザー」という機械で瓶にお湯をかけて火入れを行う方法や、湯煎する「瓶火入れ(瓶燗火入れ)」という方法があります。
瓶詰め後の火入れは、酸化を極力防げるほか、通常の火入れでは飛んでしまう香味が瓶内に保たれ、フレッシュ感が残るといったメリットもあります。
日本酒はたくさんの工程を経て造られるお酒です。また、火入れの回数やタイミング、加水の有無など、造り方の違いで特徴も変わってきます。それぞれの味わいの違いもたのしんでみてくださいね。