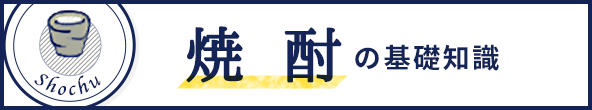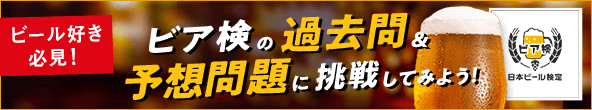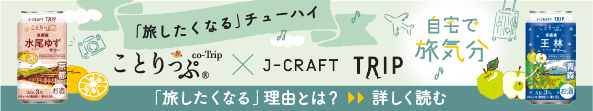黒千代香(くろぢょか)に魅せられて、鹿児島のつくり手たちに会いに行く(前編)

黒千代香(くろぢょか)は、鹿児島で古くから愛され、飲まれ続けてきた焼酎をたのしむための酒器です。黒千代香の酒器としての美しさに魅かれて、この酒器の製作に力を注ぐ陶芸家のもとを訪ねました。そして、黒千代香づくりのこだわりや技法、本場ならではの焼酎のたのしみ方について話を聞いてきました。
- 更新日:
焼酎の本場、鹿児島で生まれた酒器「黒千代香」とは

黒千代香は焼酎をお燗する器として、古くから鹿児島の人々に親しまれてきました。
焼酎にあらかじめ水を加えて(前割り)なじませておいて、黒千代香を使ってゆっくりと温め、その風味をたのしみながらいただく。それが本場・鹿児島流の焼酎の味わい方です。前割りをした焼酎は、ただアルコールの濃度が薄まるのではなく、明らかにやさしくまろやかに、そして味わい深くなるのです。
鹿児島の天文館にあるお店で、前割りにした焼酎を温めたものと、その場でポットのお湯で割ったものとを飲み比べてみましたが、その差は歴然。その場でつくったお湯割りでは、アルコールの少しとがったような刺激を感じてしまうのですが、前割りした焼酎ではそういう刺激が抑えられて、丸みのある舌ざわりと芋焼酎ならではの風味を色濃く感じることができました。
たとえば来客がある時に、あるいは仕事を終えて帰宅する主人をねぎらうために、ひと手間かけてでも、数日前から前割りを仕込んでおくというのが、焼酎を愛する鹿児島の人たちに根付いたおもてなしの作法なのかもしれません。
そして、この前割りした焼酎を温める時に使うのが、黒千代香という酒器です。囲炉裏端に黒千代香を置いて、ゆっくりと人肌に温めていただくというのが、昔ながらの焼酎のたしなみ方でした。鹿児島では土瓶のことを「ちょか」と呼び、「ちょか」の中でも焼酎をお燗する器を「黒ぢょか」と呼んでいました。鉄瓶ややかんをまねてつくられたもので、蔓(つる)を巻きつけた持ち手とこの持ち手をかける角形の耳や三つの足をつけたかたちが特徴です。
今回は、この黒千代香づくりに力を注ぐ4つの窯元を訪ねました。前編では、そのうち2つの窯元をご紹介します。
黒千代香の故郷「長太郎焼本窯」

「長太郎焼」の伝統を受け継ぐ黒薩摩の作品が展示されていました。黒千代香をはじめとする酒器のほか、壺や小皿、花瓶などの作品が並んでいました。
黒薩摩の名窯「長太郎焼本窯」を継ぐ決意
黒千代香の名付け親となったのが、「長太郎焼本窯」の初代・有山長太郎氏。それまでにも焼酎を温める酒器としての「黒ぢょか」は鹿児島の陶工たちの手によって数多くつくられてきました。その形状は、現在のものよりも胴体が長いものが多かったようです。ある朝、長太郎氏が海岸に出て桜島を眺めていたところ、錦江湾に桜島のシルエットが写りこみ、桜島とそのシルエットがソロバン玉のように見えたのだとか。この光景にヒントを得て、ソロバン玉のように鋭角な胴体を持つ「黒ぢょか」を考案。これを「焼酎が千代に香る」という意味を込めて「黒千代香」と記すことにしました。そんな初代・長太郎氏の作品を画聖・黒田清輝氏が一流と称賛し、「長太郎焼」と命名したと伝えられています。
鹿児島市谷山にあった黒薩摩の名窯「長太郎焼本窯」を受け継ぎ、四代・長太郎として窯主を務めてきたのが、有山長佑さんです。三代・長太郎、有山流石氏の長男に生まれた長佑さんですが、当初、家業を継ぐことには消極的だったと言います。このため多摩美術大学彫刻科では彫塑を学び、卒業後もしばらくは別職に就いていました。しかし、その後のヨーロッパ留学中に、四代の継承を決意することになります。
「ノルウェーの陶芸家、アーネイ・ニールセンに師事して4ヵ月を過ごした後、デンマーク、ベルギー、ドイツへと渡り、彫刻や焼き物を見てまわりました。ハンブルグに立ち寄った時に、私の好きなスイスの彫刻家、アルベルト・ジャコメッティの展覧会が開催されていることを知り、アルスター湖のほとりにある小さな美術館を訪ねました。展示された作品を鑑賞して受付に戻ると、地下フロアにある『オリエンタル・テクニカルアート・ルーム(東洋の工芸品の展示場)』の案内を目にしました。そして、日本や中国など東洋の陶器が展示された部屋に入ると、それまでに感じたことのなかった安らぎを覚え、自身が東洋の工芸品に癒されていることを感じました。焼き物屋に生まれ、幼い頃から陶器づくり触れてきた私自身の血によるものと覚悟し、家業を継ごうと決意したのです」と有山長佑さんは当時を振り返ります。
黒薩摩の伝統を継承しながら、新たな表現を追求する

有山長佑さん(左)と脇野康光さん(右)。特別に、黒千代香の製作過程を見せていただきました。
鹿児島に戻った長佑さんは、父親である三代・長太郎、有山流石氏をはじめ諸先輩たちの厳しい指導のもと、土づくりから、ろくろによる成形、釉薬の調合、焼成まで、陶器づくりの基礎から幅広く学んでいきました。なかでも、今でも心に留め、若手の指導・育成にあたってもしっかりと伝えてきたのは、一つひとつの作品を仕上げる時の、陶工としての心構えだそうです。
「私たちは、何十、何百と陶器をつくりますが、それを使う人にとっては、そのどれもが大切な一品となります。ついつい無意識に作業をしていると、その中につくり手としての魂がこもっていないものができてしまうものです。お客様にたのしんでいただくこと、その一品に愛着をもっていただくためには、つねに心のこもった品物をつくり続けなければなりません」。

青空を釉薬の色模様で再現したという「蒼碧釉」の作品。
長太郎焼の「黒薩摩」には、どこか土の温もりのようなものが感じられます。「それは代々、地元でとれた天然由来のものだけを使って調合してきたからでしょう」と長佑さん。長太郎焼で使う釉薬は、火山の噴出物が堆積したシラス層のうち、酸化鉄を多く含む層から採取した自然石と木灰とを混ぜ合わせてつくられます。通常よりも高い温度で時間をかけて焼き上げることで、やわらかで温かみのある作品を生み出しています。
こうして初代より受け継いだ「黒薩摩」の伝統を守りながら、長佑さんは、日展をはじめとする作品展にも精力的に出品し、数多くの受賞歴があります。貫入(白薩摩特有のヒビ)のない白磁のような作品づくりに挑んだり、自ら「蒼碧釉」と名づけたブルーの作品づくりに没頭するなど、84歳となった現在でも、自ら思い描く理想美の追求に余念がありません。
焼き物との対話ができる、心の余裕を大切に

「この歳になって、ようやく無心で製作に取り組めるようになった」と語る有山長佑さん(84歳)。
「20年ほど前に、当時は谷山にあった長太郎焼本窯を、中国の大使が訪れたことがありました。短時間の滞在予定でしたが、大使は『ここは落ち着くなあ』とおっしゃって、いつまで経っても立ち上がろうとはしませんでした。彼は、焼き物との対話をたのしんでいたんでしょうね」と長佑さん。訪れる人たちが焼き物との対話によって心を落ち着かせ、ついつい長居をしてしまう。長太郎焼には、そんな力が秘められているのかもしれません。
「使えば使うほどに、光沢や渋さを増して味が出てくるところに、陶器の面白さがあります。その変化を味わうために、心を整え、余裕をもって過ごしてほしいですね。焼き物との対話とは、じつは自分自身と向き合うことなんです。黒千代香から注いだ一杯を味わいながら、少しでも心が落ち着き、豊かな気持ちになっていただけたなら、つくり手としてもそれほど誇らしいことはありません」。
高齢のため、今はもうお酒を飲むこともなくなったという長佑さんですが、定期的に開催している「飲み方会」という集まりには必ず参加しています。もちろん傍らには黒千代香を置いて、持ち寄った焼酎を温めながら、友人たちとの会話をたのしんでいるそうです。肴はキビナゴのお刺身がおすすめ。酢味噌でいただくのが鹿児島流とのことでした。
〒891-0144
鹿児島県鹿児島市下福元町2962-6
TEL:099-268-3313
330年の伝統を未来につなぐ「龍門司焼」

地元産出の土と原料を使い、登り窯で焼成するのが龍門司焼の特徴。工房に併設された売り場には、黒千代香をはじめ、湯のみや皿、茶道具など、多種多様な器を揃えています。
龍門司焼の継承を決意し、伊勢に修行に出向く

2007年に改修された龍門司焼の工房。全国でも珍しくなった土間の工房を残しています。
桜島を南に臨む小高い丘の中腹(姶良市加治木町)に、龍門司焼企業組合が運営する工房はありました。龍門司焼は、16世紀末に、朝鮮半島より渡ってきた陶工たちによって始められた古帖佐焼の流れをくむ窯であり、1688年の開窯以来、330年余りの歴史と伝統技法を守り続けています。
かつては個人の陶工たちが、共同窯を使った焼き物づくりを行ってきましたが、昭和23年に龍門司焼企業組合を組織し、陶工たちは組合員として協働することになったようです。現在、この企業組合の理事長を務める川原史郎さんに、話を聞くことができました。
加治木の地に生まれ、幼い頃から土に親しみ、登り窯から立ち上がる煙や焼きあがったばかりの焼き物を間近に見て育った史郎さんは、中学生になった頃には、龍門司焼を継承しなければならないと考えるようになったと言います。21歳の時に、三重県伊勢市の「神楽の窯」に出向き、奥田康博氏に師事。全国から集まった弟子たちと互いに切磋琢磨しながら、3年3ヵ月に及ぶ厳しい修行生活を経験しました。
「奥田師匠は、非常の高い技術をお持ちの方で、日常生活を含め多岐にわたって厳しく指導していただきました。成形の技術や釉薬の調合等については師匠から学びますが、それ以外の、たとえば焼き物に対する気持ちの持ち方などは、弟子同士で熱心に語り合ったものです。同世代の陶工をめざすライバルたちの存在に、大いに刺激を受けたことを覚えています」
龍門司焼の伝統技法を、一つひとつ受け継いでいく

敷地内の登り窯。温度管理が難しく手間もかかりますが、龍門司焼独特の風合いは登り窯で焼成しなければ出せないと、今も先人たちが築いた窯を守り続けています。
龍門司焼のこだわりの一つが、粘土や釉薬の原料を、工房から半径3km以内から採取しているということ。それらを自分たちの手で集め、工房にて精製、調合しています。330年前に窯を開いた頃と同じ場所から採取し続け、現在でも原料の枯渇がないために、伝統技法に基づく、素朴で力強い風合いの器を提供できるのです。
そもそもは、龍門司焼に用いる土の収縮率が25%と極めて高いために、小物の製作が中心でした。その中で龍門司焼ならではの特色を出すために、三島象嵌、イッチン文様、飛び鉋の技法を採用したり、多彩な釉薬を使った表現したりすることで、競争力の高い製品を生み出す努力がなされてきたのです。黒釉に青流し・玉流し、白流し、鮮やかな三彩、蛇蝎釉、龍門司焼でしか見ることができない鮫肌釉などは、陶工たちが長い歴史の中で研鑽を重ね、生み出してきたものです。

黒千代香の製作にさまざまな技法を採り入れることで、多彩な表現を可能としています。
龍門司焼企業組合に戻り、理事長となってからの川原史郎さんが担ってきた重要な役割は、これら龍門司焼ならではの伝統技法に光をあて、身をもって経験しながら身につけていくことでした。もちろん、これらの技法を受け渡す後継者を育成することにも力を注いでいます。
「二人の息子たちが組合に入り、汗を流してくれているのを頼もしく感じています。一方で、330年の伝統を彼らに伝え、さらに未来へとつないでいくという責任を果たせるのかと自問自答しながら、その重圧に押しつぶされないように抵抗を続けているわけです」。
御年70歳を目前にしても、川原さんの伝統技法への挑戦は続いていきます。
陶工にとっての黒千代香とは?薩摩の焼酎とは?

土の塊が、繊細な黒千代香のかたちに整えられていく。わずか数分の出来事に目を見張るばかりでした。
「黒千代香は、庶民の暮らしに寄り添う『黒薩摩』を代表する酒器の一つ。けっして高級なものじゃなく、昔はひと窯で200、300と焼いていました。それらを鹿児島の地元の人たちがそれぞれの家庭で使うために、買っていかれた。今では、県外の方が買われることのほうが多いですけどね」。
家庭には一つあるのが普通だった黒千代香ですが、技術的には、それほど簡単につくれる器ではないようです。ソロバン状の微妙な形状を、ろくろで挽いてバランスよく美しく仕上げるためには、熟練を要します。また、蓋や耳、口や足など、後からつける部分も多く、一つの仕事の中でさまざまな要素を理解し、身につける必要があります。陶工を鍛える器なのです。
「鹿児島の人たちにとって、焼酎はどんな位置付けのお酒なのか」尋ねてみたところ、「誰もが慣れ親しんだ、欠かすことができないもの」という答えが。「夕方に、知り合いの家を訪ねると、お茶ではなくて焼酎が出てくることもあった」と、川原さんは昔を懐かしむように話してくれました。それほどに、人々の生活に深く根付いていた焼酎をおいしく味わっていただくために生まれた酒器が黒千代香であり、その製作に携わることは、鹿児島文化の継承者の一人として、誇り高いことだと語ってくださいました。
「いろんなノミカタ(宴会)に呼ばれる機会がありますが、私の場合、出されたものを出されるままに味わうことにしています。その土地の自慢の焼酎、試してほしいと思う焼酎が出てくるわけですから、それらを存分に堪能しようというわけです。料理も、焼酎をおいしくいただくために考えられた味付けが多いので、何を食べても合いますね。なかでも一番の好物は、さつま揚げです」。
〒899-5203
鹿児島県姶良市加治木町小山田5940
TEL:0995-62-2549
ライタープロフィール
川崎進