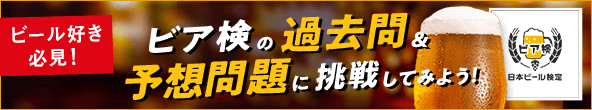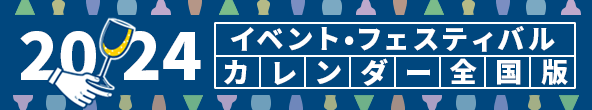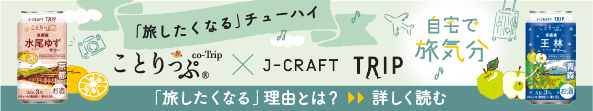時代の一歩先を行く販売戦略で出荷数を伸ばし続ける 長野・遠藤酒造場

“日本酒ブーム”といえど、年々消費量は減り、各蔵の出荷数が減り続けるなか、18年連続で出荷数量を増やし続けている遠藤酒造場。35年前、わずか500石の出荷量だった蔵を受け継ぎ、現在5500石にまで増石、信州屈指の銘酒を生み出した遠藤社長に、これまでの歩みをお聞きしてきました。
- 更新日:
目次
須坂藩に献上していた銘酒「養老正宗」
遠くにアルプス連峰を望み、いくつもの高原が広がる自然豊かな須坂市は、江戸時代、須坂藩主堀氏の館町として栄えました。1864年、庄屋を営んでいた遠藤徳三郎氏が各地を行脚していた際、おいしい日本酒に感銘を受け、「地元でも旨い酒を」との思いから自身でも酒造りを始め、酒造業がスタート。藩主に命名された「養老正宗」は評判の酒となり、献上酒として納められました。廃藩置県の後は須坂藩主跡地に会社を構え、現在に至ります。

本社のすぐ裏手にある奥田神社は、須坂藩主を祀った神社。かつて須坂藩居館だった地です。
父の急死で酒蔵に
現在社長を務めるのは六代目の遠藤秀三郎さん。地元の高校を卒業後、東京の大学へ進学。当初は酒蔵を継ぐ意思はなく、伝統産業で古くから伝わる技術で行う酒造業とは真逆の、最先端の工業技術について学んでいたそうです。
ところが、大学三年生の時に先代の父が急死。当時は経営状況から事業を縮小していたこともあり、このまま酒蔵を廃業する選択肢もありましたが、残された家族のことや、長男として生まれた責任感などから、自らが六代目となることを決意。大学を中退して故郷の須坂に戻りました。
社長業も酒造業もゼロからの出発

明るく爽やかな笑顔が印象的な遠藤秀三郎社長。社員を叱ったことがないというほど、おおらかで懐の深い六代目です。
しかし、酒蔵に戻って社長に就任したものの、つい先日まで工業技術を研究する大学生であり、さらに先代から酒造業について何も学んでいなかったことから、社長業と酒造りの両方を一から学び始めた遠藤さん。思いもかけない形で飛び込んだ世界は、苦労の連続だったと語ります。
「お酒ができても、税務署に提出する酒税の出し方もわからず、きき酒の仕方も一から教わらないといけないほど酒の知識はありませんでした。酒蔵の仕事もとにかく大変で、蔵の人たちは、日本酒を造るためにこんなことをずっと続けてきたのかと衝撃を受けました」。
当時、遠藤酒造場のお酒を扱う販売店は2軒しかなく、何軒もの酒屋に足を運んで必死に営業する毎日が続きました。「なぜうちの酒は売れないのか」。数少ない親しい付き合いのある酒販店から酒質へのアドバイスをもらい、酒蔵でそれを伝えようとするにも、従業員のほとんどは先代の父と同世代。さらに、酒造りの責任者を務めていた当時の杜氏は、酒造りへ意見されることを嫌がる昔気質の職人だったこともあり、なかなか受け入れてもらえず、遠藤社長は苦しい日々を過ごしました。
同級生を杜氏に抜擢、新ブランド「渓流」の誕生
数年が過ぎた頃、当時の杜氏が退職することになり、遠藤社長は中・高時代の同級生だった友人の勝山氏に声を掛け、蔵に迎えました。「勝山は体育教師を目指していたのですが、“一緒に日本酒を造ってみないか”と誘いました。酒造りは肉体労働ですが、日体大出身の彼なら大丈夫だろうと(笑)」。
日本酒造りは未経験だった勝山氏ですが、長野県の食品工業試験場の先生の技術指導の元、それまで前杜氏の時には造られなかった“大吟醸“の製造に取り組みます。
「前杜氏は品評会の出品に一切興味がなく、酒は二級酒をメインに造っていました。勝山が杜氏になり、酒の味が変わったことを酒販店に訴えても、以前の酒のイメージが強くそれを崩すのは難しかった。そのため、創業時からこれまでの看板商品だった「養老正宗」をやめ、新たに「渓流」という新ブランドを立ち上げました」。
ブランド力を高めるためには第三者の評価が必要と考え、積極的に品評会に出品したところ、初めて大吟醸を醸した翌年、長野県知事賞を受賞。さらに、関東信越国税局、全国新酒鑑評会など全国レベルの鑑評会でも金賞を受賞するなど実力が認められ、「渓流」は信州の人気の地酒となっていきました。

「渓流 純米吟醸 黒ラベル」
長野県産美山錦を使用し、華やかな香りと穏やかな酸味が特徴的。さらりとした口当たりとボディバランスのよさがあり、冷酒からぬる燗までおいしく味わえます。
購入はこちら

数々の品評会で受賞した際の賞状が所狭しと飾られていました。
営業をやめ、他の蔵にはない商品開発を
それまで酒販店への営業に励んできた遠藤社長でしたが、渓流ブランドを立ち上げた頃、「営業しないと売れない酒を造るのはやめよう。企画ものの商品を増やして、ブランド造りに専念しよう。」と決心し、販売戦略を一新しました。“お客さんが飲みたい商品を造ろう”と、蔵見学に来たお客さんの「搾りたてのおいしいお酒を自宅でも飲みたい」との声に、朝、搾ると同時に瓶詰めをした商品『渓流 朝しぼり』を発売。また、醪(もろみ)のおいしさを味わってもらいたいと、どぶろくのような濁りとガス感のある『どむろく』を商品化するなど、他の蔵とは違った目線で商品開発を行っていきました。
「当時、他の蔵では発売していないような珍しいお酒を商品化しました。酒販店や他の酒蔵など同業者の声はいろいろとありましたが、お客さんはおいしいといって飲んでくれる。それが自分にとっての答えでした。周囲からの意見は跳ね除けて我が道を行き、さまざまな商品開発にチャレンジしました」と遠藤社長は語ります。

「朝しぼり 出品貯蔵酒」
醪(もろみ)を低温熟成させアルコールを20%まで高め、朝搾ると同時に瓶詰して即氷冷貯蔵した逸品。甘味と酸味をバランスよく引き出した、ツウな日本酒好きに人気のお酒です。
購入はこちら

「渓流 どむろく」
瓶のなかで酵母、丸米、麹菌がすべて活性している、生きている酒。シュワシュワの発泡感、米のコクと旨味のある甘口のにごり酒は女性からも大人気です。
購入はこちら
変化するお酒売り場へ敏速な対応を
遠藤社長が自社の商品を次々と開発していたのには、ちょうどその頃、ディスカウントのチェーン店展開をする酒販店が増えてきた背景があります。
「お客さんが酒屋さんに勧められてお酒を買うのではなく、商品が並ぶ棚から自分で選んで買う時代に変化しているのを感じました。なので、ボトルへの首掛けやPOPでの商品説明などに力を入れました。ブランド力があればお客さんの手に取ってもらえる。商品のブランディングにも熱心に取り組みました」。
『渓流』のラインナップが年を追うごとに増えたことで、1998年からは18年連続で出荷数量を増やし続け、売り上げも順調に伸びているとか。日本酒の消費量が減少し、売り上げが低迷している時代にはかなり珍しいことですが、遠藤社長は、日本酒業界の先を見据えた展開を行ってきたからと語ります。
「今の世の中にぴったりのことをしていては遅いんです。次のチャネルの開拓、企画づくりを常に念頭に置いています」。
インターネット通販をいち早く行い、数年前からは社長自ら出演しTV通販も始めるなど、新たな分野にも積極的に参入しています。

お酒にはお客さんに商品をわかりやすく解説した首掛けを。
大切なパートナーとの突然の別れ
「私がブランディングや企画に集中できたのは、何より勝山が旨い酒を造ってくれたから。彼はどんどん技術を高め、県内では誰もが知る名杜氏になってくれた。絶対的な信頼があったので酒造りは彼に一任していました」と遠藤社長。
しかし、2015年、勝山杜氏は病に倒れ、帰らぬ人に。
「二人三脚で立ち上げた『渓流』がたくさんの人に愛され、会社の業績が伸びたのは勝山のおかげ。彼にはただ、感謝の気持ちしかありません」。

3年前に亡くなった勝山敬三杜氏。県内で評判の名杜氏で、遠藤社長にとっては盟友であり、大切なビジネスパートナーでした。
勝山杜氏の想いを受け継いだ若き杜氏
勝山杜氏亡き後、杜氏に就任したのは入社10年目を迎える31歳の高野伸さん。勝山杜氏が亡くなる1年前に、マンツーマンで指導を受け、3年前から杜氏として酒造りを行っています。
「勝山杜氏には、とにかくどんな小さなミスでも見逃してはいけないと指導されました。それがやがて大きなミスに繋がるからと。“酒の一滴は血の一滴”というのもよくいわれた言葉です」。
長野県内の杜氏たちから慕われていた勝山杜氏の後任にはかなりのプレッシャーがあったと話す高野杜氏。重圧から、一度は杜氏を辞退したいと社長に相談したこともあったそうです。
「勝山さんの存在が大きすぎて自分ができるか不安になりました。社長が、“バックアップするから、まずは頑張ってみよう”といってくれたので心強かったです」。
3期の造りを経験し、今は杜氏としての自信もついてきたという高野杜氏。「甘くてコクがあって、口当たりがよいのがうちのお酒のよさだと思っています。できたてのフレッシュなお酒を届けたいという社長の方針もあって、生酒の比率が多いのも特長です。これからも長野らしさのあるお酒を造っていきたいです」。

「酒造りはだいぶ大変です(笑)。でも、だからこそ楽しいです」。と語る高野伸杜氏。
年2回の蔵開きは須坂市の名イベントに
遠藤酒造場では毎年、春と秋の年2回、蔵開きのイベントを開催していますが、年々参加者が増え、今春の蔵開きでは3日間で3万5千人が来場し賑わいました。
「お酒を飲んでくれている人との接点を持ちたい」との遠藤社長の思いから2001年にスタートし、単独で3年ほど運営していましたが、4年目からは須坂市も後援となり、地域の飲食店も出店するなど、街を挙げての一大イベントとなりました。

日本酒を1杯100円でたのしめる蔵開きは3日間開催され、街の大人気のイベントに。
「地元の方たちに親しまれ、地域に根付いた酒蔵でありたいですよね。お土産にはうちの酒を選んでもらえるような、そんな地元の特産品になれたら嬉しいです」。と遠藤社長。
本社に併設している直売店には、ほとんどの商品を自由に試飲できるブースがあり、街の人が気軽に立ち寄ることも多いとか。

直営店の店内ではたくさんのお酒が試飲できます。
「酒蔵が代々続いていくには、地元の方に親しまれていることが大切。須坂市唯一の酒蔵なので、みなさんとの交流は大切にしていきたいですね」。
地元との繋がりを大切にしながら、日本酒業界のこれからを見据え、常に一歩先の展開にチャレンジし続ける遠藤酒造場は、これからも、日本酒ファンに喜ばれる酒を醸し続けます。
株式会社 遠藤酒造場
長野県須坂市大字須坂29
TEL 026-245-0117
ライタープロフィール
阿部ちあき
全日本ソムリエ連盟認定 ワインコーディネーター