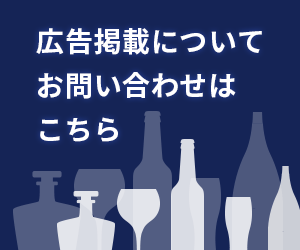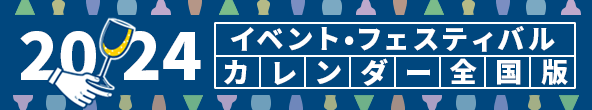樽酒とは?お祝いの鏡開きで使われる理由とたのしみ方

樽酒は木製樽で貯蔵された日本酒。香りや味わい、お祝いの鏡開き(かがみびらき)で使われる理由を解説。歴史やおいしい飲み方もご紹介します。樽酒の魅力を再発見!
- 更新日:
まずは樽酒の概要からみていきましょう。
樽酒とは? 容量のサイズは決まっているの?

えのすけ / PIXTA(ピクスタ)
はじめに「樽酒」の定義を確認します。
「樽酒」とは、木製の樽で貯蔵した木の香りがついたお酒のこと
樽酒とは、杉などで作った木製の樽に日本酒(清酒)を貯蔵して、木の香りをつけたものを指します。
日本酒の容器などに「樽酒」と表示する場合には、国税庁が示す以下の要件を満たす必要があります。
出典 国税庁告示「清酒の製法品質表示基準」樽酒の用語は、木製の樽で貯蔵し、木香のついた清酒(瓶その他の容器に詰め替えたものを含む。)である場合に表示できるものとする。
上記のとおり、樽に入っている状態のものだけでなく、木の樽で貯蔵し木の香りが移っているお酒を瓶など別の容器に詰めたものも「樽酒」と称することができます。
樽酒は、「たるざけ」のほか「そんしゅ」と読まれることもあります。
江戸時代には、兵庫の酒処・灘(なだ)で造った樽酒を船で江戸に運び、ブームを巻き起こしたと伝わります。
また、お祝いごとで行われる「鏡開き」などでは今も、「菰冠(こもかぶり)」または「本荷造り(本荷)」と呼ばれる装飾用の菰(こも/むしろの一種)を巻いた酒樽入りの樽酒が用いられています。

masayosi / PIXTA(ピクスタ)
樽酒の容量サイズはひとつに決まっている?
樽酒が入っている樽のサイズはひとつに決まっているわけではありません。大小さまざまな容量のものがあります。
サイズは、18リットル入りの1斗樽、36リットル入りの2斗樽、72リットル入りの4斗樽が一般的。9リットル入りの5升樽や3.6リットル入りの2升樽もあります。
量の目安として1杯分を120ミリリットルとして計算すると、72リットルの樽で600杯取れることになります。
一升瓶と同じ1.8リットル入りの1升樽や300ミリリットル入りのミニ樽などもありますが、これら小さなサイズのものは木製ではないものがほとんど。木香のする「樽酒」でない場合もあるので、購入する際には事前に確認するのがおすすめです。
また、容量を少なくするため上げ底している樽もあり、見かけは大きな樽のほうがよいがお酒の量はそれほどいらないといった場合に重宝されています。
なお「斗」や「升」は、かつての日本で広く使われていた「尺貫法」の単位です。詳細は以下の記事でチェックしてみてくださいね。

Artem Markin / Shutterstock.com
樽酒の香りや味わいは?
樽酒は、樽の材料である木の香りがするのが特徴のお酒です。とりわけ杉樽で貯蔵された樽酒は、すがすがしい杉の香りと、杉の芳香によりひきしめられた味わいをたのしむことができます。
また、樽で寝かせることによってまろやかさが増し、コクのある口当たりのよい味わいになるといった傾向もあります。
樽酒がお祝いごとの鏡開きで用いられるわけは?

NOV / PIXTA(ピクスタ)
お祝いごとでよく行われる「鏡開き」で樽酒が使われる理由をみていきましょう。
酒樽を開ける「鏡開き」は神事に由来
お祝いごとの席などで、菰を巻いた酒樽のふたを木槌でたたいて開ける「鏡開き」が行われることがあります。
この「鏡開き」は、祈願後に御神酒(おみき)として供えられた酒樽のふたを開け、なかの樽酒を柄杓(ひしゃく)で注いで参列者に振る舞うという、一連の神事に由来するといわれています。
酒樽のふたは、丸く平たい古鏡と形が似ているため、そのものずばり「鏡」とも称されます。そしてそのふたをたたいて抜くことを「鏡を抜く」あるいは「鏡抜き」といい、こちらが本来のいい方となります。
「鏡開き」はもともと、鏡もちを下げて食べる正月行事を指します。酒樽のふたを開ける「鏡抜き」が「鏡開き」といわれるようになった理由には、「抜く」という言葉の語感がよくないことから言い換えられたなど諸説があります。
どちらの「鏡開き」も、門出や区切りに際し、健康や幸福などを祈願してその成就を願うものに違いありません。
「鏡開き」については、こちらの記事もおすすめです。

ペコ&コロ助 / PIXTA(ピクスタ)
縁起よし! 樽酒を開ける鏡開きの掛け声とは
祝宴で樽酒を開ける鏡開きは、最初の乾杯の前に行われるのが一般的。そのときの掛け声は「よいしょ! よいしょ! よいしょ!」であることが多いようです。
1度目、2度目の「よいしょ!」のときは木槌でたたくふりだけ、3度目の「よいしょ!」でたたいてふたを割ります。
鏡開きの「鏡」は円満、「開く」は末広がりを意味しているといわれています。縁起がよいことから、結婚式でも「ご結婚おめでとうございます」の掛け声に合わせて行われることがあるようです。
樽酒の歴史とは? 江戸時代に広まったって本当?

st-kiki / PIXTA(ピクスタ)
樽酒の歴史をみていきましょう。
樽酒に使われる樽はいつ誕生? そっくりな桶とは起源が異なる!?
樽酒に使われる木製の樽は、正式には「結樽(ゆいたる)」と呼ばれるもの。杉などの板を縦に並べ、底をつけて、竹などで作る箍(たが)で締めた円筒形の容器で、ふたがついているため、液体を入れて持ち運ぶことができます。
この形の樽は、西暦113年にローマ帝国で造られたレリーフにみられることから、1世紀には誕生していたと考えられています。
日本で使われ始めたのは11世紀後半とみられ、江戸時代には酒造用としてはもちろん、農業や鉱業といった産業から一般の生活用まで、桶とともにさまざまな場面で広く使われていました。
なお、樽と、ふたがついていない桶(結桶〈ゆいおけ〉)は形がそっくりですが、それぞれまったく異なる起源を持っています。
桶は、糸の原料となる麻をしごいて出てくる細かな繊維を入れる器を起源としています。古くは結桶ではなく、杉などの薄い板を曲げて底をつけたものだったようです。
一方の樽は、液体を注ぐための容器「注器」を起源とするもので、「ものが垂れる」→「垂(た)り」→「たる」と変化していったと考えられています。

monjiro / PIXTA(ピクスタ)
樽酒が普及したのは江戸時代! 「くだらない」という言葉の語源も樽酒にあり!?
結樽に入れた樽酒が広く普及したのは、商品流通が盛んになった江戸時代のことです。
それまでお酒は、陶磁器製である甕(かめ)や箱型の「指樽(さしだる)」などの容器に入れられていました。
その後、灘をはじめとする関西地方の酒処で造られたお酒が、一大消費地である江戸に向け大量に輸送されるようになると、重くて割れやすい甕や、あまり量が入らない指樽などに代わり、軽くて量が入り、菰で巻いて保護すれば転がして運べる円筒型の結樽に入れた樽酒が普及していきます。
江戸時代、京都およびその近辺は「上方(かみがた)」と呼ばれていました。「樽廻船」という酒荷専用船で江戸に運ばれた樽酒は、灘など上方からの「下り酒」として評判を呼びます。
一方、江戸に運ばれないお酒は「下らない酒」と呼ばれていたようで、今も使われる「くだらない」という言葉の語源になったともいわれています。
なお、下り酒の代表格である灘酒の詳細は、こちらから確認できます。
樽酒をおいしく飲もう!

Nori / PIXTA(ピクスタ)
樽酒は、樽に入った状態で振る舞われる場合には常温で飲むことがほとんどだと思われますが、じつは冷酒や燗酒でもたのしめるお酒です。
常温ではまろやかさが感じられる樽酒を冷やして飲むと、のど越しのよさが増します。また、40度前後のぬる燗くらいまで温めると、お酒に移った木樽のよい香りがより引き立ちます。
瓶やカップ、紙パックに詰められた樽酒の飲みごろは、一般的な日本酒と同様、開封前であれば、冷暗所で保管のうえ、製造年月から8カ月~1年程度を目安と考えてよいでしょう。
一方、樽に詰められたまま振る舞われる樽酒は傷みやすく、そのままにしておくとお酒に移った木の香りが強くなりすぎてしまうため、開封前のものでも夏場で2週間程度を目安としましょう。
開封後は、瓶などに詰めたもの、樽に詰めたものにかかわらず、なるべく早めに飲み切るのがおすすめです。
なお、振る舞い酒は、升に注がれることも多いものです。升酒は飲みやすそうな角ではなく、平らな部分に口をつけて飲むのが正式な飲み方とされています。仲間内での飲み会ではそれほど気にすることはありませんが、招待された祝宴などでは角から飲んでしまわないよう気をつけましょう。
升酒についてはこちらの記事でも取り上げています。
瓶などに詰められている樽酒は入手しやすく、すがすがしい木の香りやまろやかな味わいが手軽にたのしめます。また、樽詰めの樽酒は、祝宴のほか、神社の初詣や蔵元が行うイベントなどでも振る舞われます。機会に恵まれたときには、存分に味わってみてくださいね。