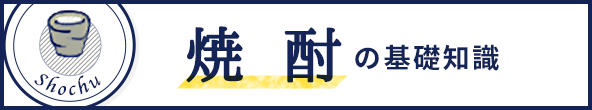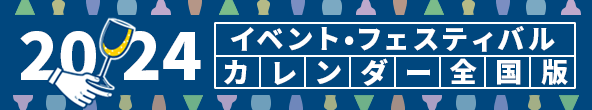沖縄名産「泡盛」の原料は? なぜタイ米が使われる? ラベルの「原材料:米麹」ってどういう意味?

「泡盛」は米を主原料に造られる蒸溜酒で、酒税法上は焼酎に分類されます。今回は泡盛の原料に着目し、国産米ではなくタイ米が好まれる理由や、黒麹菌が使われる理由、ラベルに書かれた「原材料:米麹」の意味、3年以上熟成させた「古酒(クース)」の魅力などを紹介します。
- 更新日:
目次
「泡盛」の個性的な味わいを特徴づける原料についてみていきましょう。
「泡盛」の酒税法上の分類は単式蒸留焼酎!? まずは定義をおさらい

masakun / PIXTA(ピクスタ)
「泡盛」は沖縄の伝統的なお酒で、日本の酒税法では「焼酎」に分類されています。
焼酎は酒税法上、連続式蒸留機で蒸留したアルコール分36度未満の「連続式蒸留焼酎」と、単式蒸留機で蒸留したアルコール分45度以下の「単式蒸留焼酎」の2つに区分されますが、昔ながらの単式蒸溜で造られる泡盛は「単式蒸留焼酎」に含まれます。
単式蒸留焼酎には泡盛のほかにも、芋焼酎や米焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎、そば焼酎などさまざまな種類があります。なかでも米や麦などの穀類や芋類、清酒かす、黒糖のほか、国税庁長官が定めた原料と麹を使用し、水以外の添加物を使わないものを「本格焼酎」と呼びます。泡盛も分類上は本格焼酎の一種です。
なお、泡盛に酒税法上の明確な定義はありません。一般的には以下の特徴を持つお酒を「泡盛」と呼んでいます。
◇主原料に米を使う
◇種麹に黒麹菌を使う
◇全麹仕込み
◇単式蒸留機で蒸留する(単式蒸留焼酎である)
泡盛の特徴や本格焼酎については、以下の記事でくわしく紹介しています。
「泡盛」の原料1〜お米〜

nanD_Phanuwat / PIXTA(ピクスタ)
「泡盛」の主原料といえばお米です。
泡盛の主原料にはおもにタイ米(インディカ米)が使われる
「泡盛」と同じくお米を主原料に造られる焼酎に「米焼酎」がありますが、米トレーサビリティ法により原産国表示が義務づけられたことで国産米(ジャポニカ米)への切り替えの動きがみられた米焼酎に対して、泡盛では伝統的に長粒種のタイ米などのインディカ米が使われています。
タイ米は粘り気のある国産米に比べてサラサラして扱いやすく、麹菌が付着しやすいという特性があります。また、発酵過程では温度管理がしやすく、多くのアルコールを生成するのも特長です。
特筆すべきは、泡盛にバニラ香と表現される芳醇な香りをもたらすこと。タイ米の個性は、製麹のしやすさはもちろん、泡盛の香りや味わいにも息づいているのです。
なお、「泡盛」といえばタイ米というイメージが強いかもしれませんが、国産米を使ってはいけないという決まりはありません。近年は地元沖縄で栽培されたジャポニカ米で造る泡盛も登場し、注目を集めています。

akhorn2538 / PIXTA(ピクスタ)
泡盛でタイ米が主流になったのは昭和以降
「泡盛」は日本でもっとも古い歴史を持つ蒸溜酒ですが、現在の原料と製法で造られるようになった時期や背景は謎に包まれています。一時は地域で栽培されたお米やキビ、さつまいもが使われていたという情報や、原料に粟(あわ)を使用していたことから「アワモリ」と呼ばれたという説があるように、ずっと昔からタイ米だけを主原料に造られていたわけではないようです。
泡盛にタイ米が使われるようになったのは、1920年代の初頭のこと。それまで使用していた唐米の価格が高騰したため、アジアの各地から米を輸入するように。なかでも泡盛の造り手たちが質の高さを保てる主原料を求めてたどり着いたのが、タイから輸入したインディカ米でした。
大正末期からタイ米の輸入が始まり、昭和初期には泡盛の原料として沖縄の地に定着。このころには、粟などを混ぜないタイ米だけを使った製法が根づいていたといいます。
近年では、タイからの輸入米だけでなく、泡盛造りに適した地元産のインディカ米を使って泡盛を造る蔵元も登場しています。
泡盛の原料2〜黒麹菌〜

リュウ / PIXTA(ピクスタ)
「泡盛」造りに欠かせない原料のひとつに「黒麹菌」があります。
沖縄の風土に適した麹菌
「黒麹菌(黒麹)」とは黒いコウジカビのことで、泡盛の発酵に欠かせない原料です。
黒麹菌は、麹造りに使われる種麹(たねこうじ)の一種で、主原料に含まれるデンプンを糖に分解する役割があります。この糖が発酵によってアルコールに変わります。
種麹には、黒麹菌のほかに、日本酒造りに使われる「黄麹菌」、黒麹の突然変異から生まれた「白麹菌」がありますが、白麹菌が見つかるずっと以前から、泡盛には伝統的に黒麹が使われてきました。当時は桑の木の幹から採れる黒いカビを使っていたそうで、のちの調査でここから沖縄固有の菌種・黒麹菌(Aspergillus Awamori/アスペルギルス・アワモリ)が見つかっています。
黒麹菌には、デンプンを糖に変えるだけでなく、クエン酸を大量に分泌するという特徴があります。沖縄のように温暖で湿度が高い地域では雑菌が繁殖しやすく、発酵中の原料(もろみ)が腐ってしまう危険性がありますが、クエン酸が持つ防腐作用のおかげで、常夏の沖縄でももろみの腐敗を防ぐことができたといわれています。
黒麹菌は泡盛の味わいを特徴づける重要な要素
黒麹菌で造ったお酒は、芳醇な香りとコクを特徴に持つ傾向があります。「泡盛」独特の香りや味わいにも黒麹菌らしさが生きており、泡盛の味わいを特徴づける重要な要素と考えられています。
とりわけ、後味のビターさは黒麹菌ならではの魅力といわれています。
泡盛のラベルにある「原材料名:米こうじ(タイ産米)」ってどういう意味?

Michaela Warthen / Shutterstock.com
「泡盛」のラベルに「原材料名:米こうじ(タイ産米)」と表示されている理由は、泡盛独特の製法にありました。くわしくみていきましょう。
「泡盛」の「原材料名」とは?
お酒のラベルには、名称や品目、内容量、アルコール分、品目などとともに「原材料名」の表記が法令で義務づけられています。一般的な本格焼酎の場合は、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示しなければなりません。
たとえば、芋と米麹を原料に造る芋焼酎なら「原材料名:さつまいも(国産)・米こうじ(国産米)」、米と米麹を原料に造る米焼酎なら「原材料名:米・米こうじ(国産米)」のように表記されます。
「泡盛」に関しては、「泡盛の表示に関する公正競争規約」によって「原材料名:米こうじ」と表示することが義務づけられています。
実際には、泡盛を含む米を使用した単式蒸留焼酎が「米トレーサビリティ法」の対象品目に指定されていることから、
原材料名:米こうじ(タイ産米)
のように、米の原産地を表示する必要があります。
(参考資料)
一般社団法人 全国公正取引協議会連合会|泡盛の表示に関する公正競争規約・施行規則

kai / PIXTA(ピクスタ)
「泡盛」独特の「全麹仕込み」とは?
一般的な本格焼酎の原材料が「主原料+麹」なのに対して、泡盛の原材料は「米麹」のみ。その秘密は、泡盛の特徴のひとつ「全麹仕込み」にあります。
一般的な本格焼酎は、米や麦など麹の原料に種麹をつけて米麹や麦麹などの麹を造り、そこに水と酵母を加えて1次もろみを造り(1次仕込み)、さらに主原料を仕込んで発酵させ、2次もろみを造ります(2次仕込み)。
一方、泡盛では主原料の米を黒麹菌ですべて米麹に変え、そこに水と酵母を加えて一度の発酵でもろみを造ります。これが「全麹仕込み」です。
泡盛は、タイ米と黒麹で造られた米麹だけで仕込まれるお酒。2度の仕込みではクエン酸濃度が薄まることから、腐敗を防ぐ策として「全麹仕込み」が根づいたといわれています。
なお、「全麹仕込み」自体は泡盛独特の仕込み法ではありません。
さとうきびを原料に使った泡盛もある?

galitskaya / PIXTA(ピクスタ)
沖縄の名産品に、「ウージ」の異名で知られる「さとうきび」があります。搾り汁からは砂糖や黒糖が作られ、その副産物として糖蜜が採れますが、黒糖は黒糖酒やラムの原料に、糖蜜は甲類焼酎の原料として使われたとしても、泡盛の原料になることはありません。
ちなみに、沖縄で獲れるさとうきびは、おもにグラニュー糖や黒砂糖の原料に用いられます。副産物の糖蜜は、バイオエタノールの原料や動物のえさに使われています。
3年以上熟成させた「古酒(クース)」なら泡盛の原料の魅力がさらに際立つ

omizu / PIXTA(ピクスタ)
「泡盛」を3年以上貯蔵したものを「古酒(クース)」と呼びます。「古酒」は熟成年数が長いものほどおいしいといわれ、琉球王朝時代は王府への献上品にも用いられていました。
タイ米と黒麹菌がもたらす芳醇な味わいは、熟成の時を経るごとに熟成香をまとい、口当たりもまろやかに変化します。泡盛の原料ならではの奥深い魅力を味わいたい人は、ぜひ古酒も味わってみてください。
泡盛の泡盛らしさを育んでいるのは、原料となるタイ米や米麹、それらの個性を活かす「全麹仕込み」はもちろん、南国・沖縄の風土や、琉球王朝時代から培われてきた伝統や食文化も大きな要素です。これら多くの要素によって導かれる泡盛の魅力を、ぜひ味わってみてください。