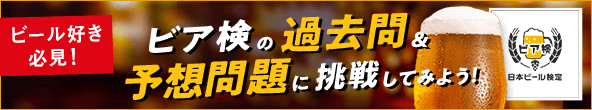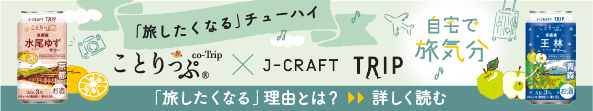ビールと酒税、気になる関係を徹底解説!

「酒税」はお酒の値段に深く関わっていて、酒税を定める「酒税法」が改正されるたびに、大きな影響を及ぼしてきました。2018年4月の改正では、ビールの値段はもちろん、ビールの定義にも大きな変化がありました。ここでは、ビールに関わる酒税法改正の推移について、将来の予定も含めて紹介します。
- 更新日:
目次
ビールと酒税の歴史を振り返る

Lamberrto/ Shutterstock.com
酒税が日本に登場したのは室町時代のこと
「酒税」とは、お酒にかかる税金のことで、それを定めた法律が「酒税法」。この法律によって、ビールや日本酒、ウイスキーなど、お酒の分類が細かく定義され、その分類に応じて税率が定められています。
日本における酒税の歴史は古く、初めてお酒に課税されたのは室町時代と言われています。その後、江戸時代になると、幕府が酒造の統制を目的に「酒株(さけかぶ)」と呼ばれる免許制度を設け、酒株を持つ酒造業者に「運上金(うんじょうきん)」を課していました。
明治の酒税法改革により、ビールにも税金が
酒税に関する法制度が整備され始めたのは、明治を迎えてからのこと。1871年(明治4年) に酒株制が廃止され、免許料を払えば誰もが酒造業に参入できるようになり、1875年に「酒類税則」、1880年には「酒造税則」が制定されました。
その後、日清・日露戦争を背景とした軍備拡張に向けて、大規模な増税を必要とした明治政府は、1896年に「酒造税法」を制定。以降5年間で3度にわたる増税を実施しました。
さらに5年後の1901年には、それまで酒税の対象外だったビールにも「麦酒(ビール)税」が導入されました。
ビールの税率は酒類のなかで突出して高い
酒税法が現行のものに切り替わったのは、第二次大戦後の昭和28年(1953年)のこと。その後も大小さまざまな改正が繰り返されながら、現在に至っています。
基本的にはアルコール度数の高さに応じて税率が設定されてきましたが、ビールは比較的アルコール度数が低いにもかわらず税率は高め。しかも昭和50年代だけで4回も税率が引き上げられるなど「税率の高止まり」とも言える状況が続いています。
これは、ビールの消費量が日本酒を抜いて酒類のトップになったことで、税収源として旨味があると見なされたためではないかとも言われています。
酒税法による税率の違いが「発泡酒」や「第3のビール(新ジャンル)」を生んだ

jointstar/ Shutterstock.com
酒税法では「ビール」と「発泡酒」は税率が異なる
酒税法では、「ビール」と「発泡酒」は別物として区別され、税率も異なります。
ビールの税率が高止まりするなか、低価格競争を続けていたビールメーカーから「ビールよりも税率の低い発泡酒で、ビール同様の味わいができないだろうか?」との発想が生まれました。
各メーカーが工夫を重ねて生み出した「ビール風味の発泡酒」は、90年代半ばごろから市場に出回り始めると、ビールの半分程度というオトク感と、ビールに引けを取らないおいしさと感じる人も多かったのか、“家計の救世主”として好意的に受け入れられました。
発泡酒の税率引き上げが「第3のビール(新ジャンル)」を生んだ
低価格な発泡酒の売上が拡大するにともない、ビールの消費量は下降線をたどり始めます。これは国税庁にとって憂慮すべき事態だったようで、ビールの税収が落ち込んだ分を取り戻そうとするかのように、発泡酒の税率は10年間で2度も引き上げられました。
そこで、ビールメーカーはさらに工夫を凝らします。麦芽以外の原料を用いたり(酒税法上は「その他の醸造酒」に分類)、ビールや発泡酒に別のアルコール飲料を混ぜたり(「リキュール」に分類)して、ビールや発泡酒よりも税率が低く、それらと同様の味わいがたのしめるようにと、「第3のビール(新ジャンル)」を開発したのです。
2018年の酒税法改正でビールの定義が変更!

Luca Santilli/Shutterstock.com
酒税法改正でビールの定義はどう変わった?
酒税法の改正はその後も続きます。なかでも大きかったのが2018年4月の改正で、これによりビールの定義が変更となりました。
それまで、ビールの定義は「麦芽比率67%以上」が必須でしたが、これが「50%以上」に緩和。また、主原料の5%という範囲内で使用が認められる「副原料」について、従来からの麦や米などに加え、規定された果実や香味料なども認められるようになりました。
これにともない、これまで「発泡酒」に分類されていたものでも、麦芽比率が50%以上で、認められた副原料を使用しているものであれば、「ビール」として扱われるようになったのです。
酒税法の改正がビールの可能性を広げる?
2018年の酒税法改正により、ビールの定義が大きく拡大されたことを受けて、たとえばフルーツテイストのビールなど、より多様なビール造りが活発化しています。
また、輸入ビールのなかには多様な副原料が使われている商品もあり、これまでは日本では税制上「ビール」ではなく「発泡酒」として販売されてきましたが、改正後は、麦芽比率が50%以上であれば「ビール」として販売できるようになりました。
国産・輸入ともに、より多様なビールがたのしめるようになり、その相乗効果で新たなビール開発が進むことが期待されます。
酒税法はビールの価格だけでなく製造免許も左右

Poliakphoto/shutterstock.com
酒税法の改正が生んだクラフトビールブーム
酒税法は、お酒の定義や税率だけでなく、酒類の製造免許についても規定しています。
ビールの製造免許を取得するには、一定程度の生産量が条件とされています。かつては年間2,000キロリットル以上(350ミリリットル缶で約571万缶)、つまり365日、年中無休で造っても毎日650ケース以上の製造・販売能力が必要という途方もない条件で、事実上中小メーカーの参入が不可能でした。
1994年の酒税法改正により、ビールが年間60キロリットル、発泡酒が同6キロリットルへと大幅に引き下げられたことで、小規模なブルワリーが全国各地に誕生。個性的なビール造りが注目され、クラフトビールブーム到来の一因となりました。
酒税法改正によるマイクロブルワリーへの影響を配慮
2018年の酒税法改正でビールの定義が広がることを知った中小ブルワリーの間に、ある懸念が広がっていました。今まで「発泡酒」として製造していたものが「ビール」扱いとされることで、年間の最低製造量がビールと同じ60キロリットル以上に引き上げられるのでは、というものです。
実際には、発泡酒免許で製造しているマイクロブルワリーが多いことに配慮し、「新酒税法ではビールと定義されるものでも、免許取得時に発泡酒とされていた場合は、引き続き発泡酒免許で製造・販売が可能」としています。これを受け、法改正前には駆け込みで製造免許を取得する個人や企業が増加しました。ビールの定義拡大と合わせて、クラフトビール開発のさらなる活性化が期待されています。
酒税法とビールのこれから

Tortoon/shutterstock.com
酒税法でのビールや発泡酒、第3のビールの税率も変化
2018年の酒税法改正では、ビールと発泡酒の定義を変更すると同時に、第3のビール(新ジャンル)も含めて、税率が以下のように変更されました(350ミリリットル缶で換算)。
ビール(麦芽比率50%以上)/約77円
発泡酒(麦芽比率25~50%)/約77円
発泡酒(麦芽比率25%未満)/約47円
第3のビール(新ジャンル)/約28円
酒税法の最終目標はビール系飲料の税率一本化
近年の酒税法改正の大きな目的は、バラバラだったビール系飲料の酒税を統一化することにあります。今後、上記の税率は段階的に変更され、2026年には約55円に統一される計画で、ビールにとっては値下げ、それ以外は値上げとなります。
これにより、ビールメーカーの開発テーマは「いかに低い税率で、いかにビールに近づけるか」という視点がなくなり、純粋に品質や魅力的なストーリーが問われる時代になっていきそうです。
酒税法の改正とともに、ビール業界は大きく変化してきました。これから予定される税率の一本化を控えて、どのような変化が生じるでしょうか? ビール好きにとっては目が離せませんね。
国税庁サイト:酒税法等の改正のあらまし

おすすめ情報
関連情報
ビア検(日本ビール検定)情報