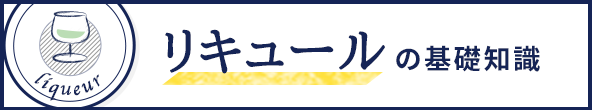梅酒の作り方を紹介!材料や道具、おすすめの作り方、ベースとなるお酒の選び方、酒税法上の注意点まで紹介

梅酒は作り方がとてもシンプルで、自宅でも手軽に漬けることができます。ここでは、自家製梅酒をたのしむために知っておきたい酒税法上の注意点やレシピ、梅や氷砂糖などの材料、竹串などあると便利な道具、ベースに用いるお酒の種類、おいしく仕上げるコツなどを紹介します。
- 更新日:
梅酒は自宅でもかんたんに作れる日本の代表的なリキュールです。梅酒作りに挑戦する前に、梅酒の基本情報と酒税法上の注意点を確認しておきましょう。
梅酒とは日本を代表するリキュール

kai keisuke / Shutterstock.com
梅酒は日本の代表的なお酒。梅の実を糖類と一緒にお酒に漬けて、じっくり寝かせるだけと作り方もかんたんで、ロックや水割りやソーダ割りなど多彩な飲み方ができることから、広く親しまれています。
梅酒の原料である梅は、バラ科の落葉高木です。梅にまつわる最古の記録は、紀元前2000年ごろの中国の商書に残された「塩梅」の記載。原産国の中国から日本へ渡ってきたのは弥生時代のことで、以来、漢方薬や保存食として重宝されてきました。
梅酒がいつ、どのようにして生まれたのかは、残念ながら記録に残されていません。しかし、元禄時代に刊行された江戸時代の書物書『本朝食鑑』に梅酒の作り方が紹介されていることから、300年以上前から飲まれていたと考えられます。
なお、梅酒は「酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの」に該当することから、日本の酒税法ではリキュールに分類されます。
梅酒を自宅で作るには酒税法上の注意点がある

Billion Photos / Shutterstock.com
果実酒などは多くの場合、自宅で作ることが法律で禁止されています。たとえば、ワインにフルーツやスパイスを漬けて作るサングリア。本場スペインでは、ワインにフルーツや糖類、スパイスなどを加えて、果実の味がしみ出るまで漬け込むレシピが主流ですが、日本ではワインにフルーツなどを混ぜ合わせる「混和」という作業がお酒の製造とみなされ、「自家用かつ混ぜ合わせてからすぐに飲む」などの場合を除き、酒税法に触れることになります。そもそもお酒を製造するには、税務署長の付与した酒類製造免許が必要だからです。
梅酒もサングリア同様、お酒に梅や糖類を混ぜ合わせて作りますが、こちらは酒税法で定められた以下の条件をクリアすることで、家庭で作ることが例外的に認められます。
<梅酒を自宅で作るための条件>
◇自分で飲むためのお酒であること
◇アルコール分20度以上、かつ酒税が課税済みの酒類を用いること
◇お酒に混和する物品が以下の物品に該当しないこと
(1)米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、もしくはでん粉またはこれらのこうじ
(2)ぶどう(やまぶどうを含む)
(3)アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料または酒類のかす
(参考資料)
国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)」/自家醸造
サングリアと梅酒の決定的な違いは、ベースとなるお酒のアルコール度数です。サングリアに使われるワインのアルコール度数は12度程度。20度を超えるものもありますが主流とはいえません。一方、梅酒のベースに広く使われる蒸溜酒はアルコール度数20度以上が一般的で、梅酒作りに使用されるのはアルコール度数35度のホワイトリカー(甲類焼酎)が主流になっています。
余談ですが、1962年の酒税法改正以前は、梅酒も一般家庭で作ることが禁止されていたそう。現在は誰でも手軽に自家製梅酒を作れるので、酒税法に抵触しないよう注意しながらたのしみたいですね。
梅酒作りに必要な材料と道具

ノンタン / PIXTA(ピクスタ)
梅酒作りに必要な材料と、用意しておきたい道具を紹介します。
梅酒のおもな材料は青梅と氷砂糖とお酒
梅酒作りに使う材料は、おもに以下の3つです。
◆青梅
◆氷砂糖
◆お酒
水などは一切加えません。
ベースとなるお酒は焼酎などの蒸溜酒を使うのが一般的ですが、アルコール度数20度以上の日本酒(醸造酒)などを使用するケースもあります。
ベースに使うお酒のおすすめはホワイトリカー(甲類焼酎)
梅酒作りに使用するお酒のおすすめは、ホワイトリカーです。
ホワイトリカーとは、梅酒などの果実酒作りに用いられる、限りなく無味無臭の焼酎のこと。焼酎は連続式蒸溜機で造られる甲類焼酎と、昔ながらの単式蒸溜機で造られる乙類焼酎(本格焼酎)に大別されますが、ホワイトリカーは甲類焼酎にあたります。
麦焼酎などの本格焼酎を使ってもおいしく仕上がりますが、多くの場合は雑味のないクリアな味わいのホワイトリカーが使われます。
なお、自家製梅酒のアルコール度数は、ベースに用いるお酒のアルコール度数によって変わります。材料の分量によっても若干の差異はありますが、以下を目安にチョイスしてみてください。
◇ベースのお酒のアルコール度数が35度の場合
⇒アルコール度数25度程度の梅酒が完成
◇ベースのお酒のアルコール度数が25度の場合
⇒アルコール度数15度程度の梅酒が完成

ツルカメデザイン / PIXTA(ピクスタ)
保存用の容器と梅の下処理用の竹串を用意する
梅酒作りには以下のような道具も必要です。
◆果実酒用の保存容器
◆梅の下処理用の竹串
◆清潔な布巾、またはキッチンパーパー
容器は透明で中身が見える果実酒用のものを選びましょう。梅をお酒に漬け終えたら、成分を抽出するために容器の中で数カ月寝かせるので、密閉できることも重要な条件です。
竹串はつまようじ(爪楊枝)でも代用可能ですが、下処理をする梅の量が多い場合は、ある程度強度があって持ちやすい竹串や、焼き鳥に使用する鉄砲串が便利です。
布巾は梅の水気を取るのに使用します。乾いたものを用意しましょう。キッチンペーパーでの代用も可能です。
自宅でかんたんに作れるおすすめの梅酒レシピ

SoutaBank / PIXTA(ピクスタ)
ここでは、4リットル容器を使用した場合の、梅酒の作り方を紹介します。
<用意するもの>
青梅…1キログラム
氷砂糖…700グラム ※お好みで増減してください
ホワイトリカー…1.8リットル
容器(4リットル)
竹串…数本
布巾またはキッチンペーパー
<作り方>
1.保存用の容器はきれいに洗って水気を完全に取り除いておきます。その際、アルコールで消毒しておくと完璧です。
なお、ホワイトリカーもアルコールですが、消毒効果が期待できるほどの度数ではありません。アルコール度数70〜80度程度の食品用アルコールを使用しましょう。
2.青梅の表面を傷つけないようやさしく水洗いし、2時間ほど水に漬けておきます。その後清潔な布でひとつひとつ水気を拭き取り、竹串の先で青梅のヘタを取ります。
3.乾いた容器に梅と氷砂糖を交互に入れていきます。
4.青梅と氷砂糖を入れた容器にホワイトリカーを静かに注ぎます。
5.ふたをしっかり閉めたら、冷暗所で数カ月保存します。時間が経つごとに氷砂糖が溶けていくので、液中の糖分が均一になるよう、週に数回容器を静かに回しましょう。梅のエキスがしみ出たら完成です。
自家製梅酒をおいしく仕上げる作り方のコツ

Pachira1 / PIXTA(ピクスタ)
梅酒の作り方を確認したら、好みの味に仕上げるポイントをみていきましょう。
ポイント①|梅酒作りに適した時期と飲みごろ
梅酒の材料になる青梅はいつでも手に入るわけではありません。春を待たずに花を咲かせた梅の木は、ミツバチの力を借りて実を結びます。春の日差しに育まれた梅が旬を迎えるのは5〜7月ごろのこと。新鮮な梅が入手できるこの時期こそが、梅酒作りに適した季節といえるでしょう。
梅の旬の時期に作った梅酒は3カ月ほどで飲めるようになりますが、半年、1年と寝かせるといっそうおいしく仕上がります。2年以上熟成させる場合は、1年ほど経ったころに梅を容器から取り除いておきましょう。
ポイント②|青梅の選び方は?完熟梅という選択肢もある
梅にはさまざまな種類があり、実梅(みうめ)の品種だけでも100種ほど存在するといわれています。
梅酒作りに適しているのは、果肉が多い大粒の梅。なかでも人気が高いのは「南高梅(なんこうばい)」という高級品種です。
梅の品種によって味わいが異なるので、いろいろ試してお気に入りを探してみてください。
なお、一般的な梅酒のレシピでは青梅を使用しますが、完熟梅を使うケースも増えているようです。青梅で作った梅酒はすっきりとした味わいに、完熟梅を使った梅酒は芳醇な風味の梅酒に仕上がる傾向があります。

travelwild / Shutterstock.com
ポイント③|氷砂糖の代わりに黒糖を使った黒糖梅酒も人気
氷砂糖の代わりに、グラニュー糖やザラメ、てんさい糖、黒糖、はちみつなどを使用すると、王道レシピとは異なる味わいがたのしめます。なかでもおすすめは、黒糖を使った黒糖梅酒。黒糖独特のコクのある甘味がクセになるので、機会があったら試してみてください。
ポイント④|ベースのお酒選びで味わいは大きく変わる
梅酒の味わいをもっとも大きく左右するのが、ベースとなるお酒の種類です。一般的に、自家製梅酒には以下のようなお酒が使われます。
◇ホワイトリカー(甲類焼酎)
ホワイトリカーはクセがないので、梅本来の風味をたのしめるほか、割り方を選ばないという特長もあります。
◇ブランデー
深みのある味わいをたのしみたい人には、ブランデーの使用がおすすめ。ブランデーで作る梅酒は熟成が早く、ホワイトリカーの半分ほどの期間で飲みごろを迎えます。
◇ウイスキー
ウイスキーで作る梅酒は、コクのある味わいに仕上がる傾向があります。ブランデーと同様に、熟成が早いのも魅力です、
◇日本酒(アルコール度数20度以上)
日本酒で作る梅酒は、よりまろやかな味わいが特徴。梅の酸味と米の甘味のハーモニーがたのしめます。

NPDstock / PIXTA(ピクスタ)
ポイント⑤|梅酒の保存期間と保存方法は?容器に入れたら冷暗所でじっくり寝かせよう
梅酒の保存期間は最短で3カ月ほど。前述したように、半年、1年…と熟成させることで、よりおいしくなります。
といっても、これは適切な場所に保存した場合の話。悪条件で保存すると梅の成分が抽出される前に劣化してしまうおそれもあるので、正しい保存方法を確認しておきましょう。
◇梅酒ができるだけ空気に触れないよう、容器はしっかり密閉しておく
◇光に触れない冷暗所に保存する
◇温度変化の多い場所は避ける
数カ月先においしく味わうためにも、保存方法にはこだわりたいですよね。
梅酒の個性は、梅の品種や糖の種類、ベースとなるお酒の種類で変化します。好みの組み合わせを知るのに手っ取り早いのが、市販の梅酒の飲み比べ。いろいろ試して、オリジナルの梅酒レシピを作ってみてください。