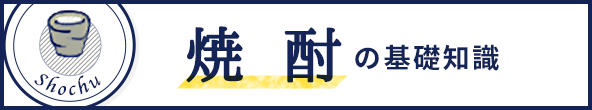焼酎に「賞味期限」はある?未開封・開封後の違いと適切な保存方法も紹介

焼酎には「賞味期限」がありません。基本的には開封・未開封を問わず時間が経っても飲めますが、保管・保存状態によっては品質が劣化するおそれもあります。今回は、焼酎に賞味期限がない理由や焼酎の適切な保管・保存方法について紹介します。
- 更新日:
焼酎には賞味期限の記載がありませんが、なぜなのでしょうか。
焼酎に賞味期限がない理由

タカス / PIXTA(ピクスタ)
焼酎には、賞味期限や消費期限がありません。
賞味期限とはおいしく食べたり飲んだりできる期限、消費期限は安全に食べたり飲んだりできる期限を指しますが、焼酎にはどちらの年月日も設定されていません。
お酒は嗜好品。おいしく飲めることが重要なので、ここから先はおいしく飲める期限「賞味期限」に特化し、焼酎に賞味期限がない理由や記載がない理由、ラベルに書かれた日付の意味などをみていきます。
焼酎やウイスキーなどの蒸溜酒には賞味期限がない
焼酎には賞味期限がありません。同様に、ウイスキーやブランデー、ウォッカ、ラム酒、ジン、テキーラなどのお酒にも賞味期限がありません。そのおもな理由に、これらのお酒が蒸溜酒だからということが挙げられます。
焼酎やウイスキーなどの蒸溜酒は、蒸溜の過程で不純物が取り除かれます。細菌のエサになる不純物がなければ、腐る心配はないということです。また、蒸溜によってアルコール分を濃縮しているため、当然ながらアルコール度数が高くなりますが、アルコールには殺菌作用もあるため、基本的には雑菌が繁殖する余地もありません。
焼酎をはじめとした蒸溜酒に賞味期限が必要ないのは、こうした理由からです。

kotoru / PIXTA(ピクスタ)
焼酎のラベルに賞味期限の記載がないのは省略が認められているから
焼酎のラベルやパッケージには賞味期限の表示がありません。焼酎には賞味期限がないのだから当然といえば当然なのですが、記載がないのは「蒸溜酒だから」というわけではありません。
賞味期限の記載がないことの理由を知るには、消費者庁が食品衛生法の規定にもとづき策定した「食品表示基準」という内閣府令をひもとく必要があります。
一般消費者が購入できる食べ物や飲み物、いわゆる「一般加工食品」には、商品の特性に応じて「賞味期限」か「消費期限」のいずれかが表示されています。これらの期限の表示については、「食品表示基準」の第三条で細かくルールづけされていますが、なかには例外的に賞味期限や消費期限を省略することが認められたものもあります。「酒類」もそのひとつです。
「酒類」というからには、焼酎やウイスキーなどの「蒸溜酒」だけでなく、ビールやワイン、日本酒といった「醸造酒」や、お酒に糖類その他物品を混ぜたリキュールなどの「混成酒」も含まれます。なかには、アルコール度数が高いとはいえないお酒もありますが、いずれも賞味期限の表示は省略可とされています。
ビール酒造組合に所属している大手ビールメーカーでは、組合が定める「ビールの表示に関する公正競争規約」にもとづきビールに賞味期限を表示していますが、その他のメーカーが造るビールやベースの焼酎にアルコール以外のものを混ぜたスピリッツやリキュールの場合は、製造元が自主的に賞味期限を表示しているケースもあるようです。
(参考資料)
e-GOV法令検索|食品表示基準
国税庁酒税課|食品表示法の概要(酒類表示編)

Mattz90 / Shutterstock.com
焼酎のラベルに書かれた日付の意味は?
焼酎のラベルやパッケージには、日付を表す数字が記載されていることがあります。この日付は必ず過去のものになっているため「賞味期限が過ぎているの?」とあせった経験がある人もいるのではないでしょうか。
焼酎のラベルに印字されている日付は、賞味期限ではなく詰口年月日と呼ばれるもので、蔵元で瓶詰め(パック詰め)が行われた年月日のこと。法律や内閣府令などで表示が義務づけられているわけではなく、造り手が自主的に記載しているもので、「焼酎ヌーボー(ヌーヴォー)」や「新酒」と呼ばれる、特定の時期にしか味わえない限定品でない限り、この日付を気にする必要はありません。
瓶詰めから年月が経った焼酎は飲める?

ひとり君 / PIXTA(ピクスタ)
焼酎などの蒸溜酒には賞味期限がないといっても、未開封のまま数年が経過したものや、開栓後のものなど、瓶詰めから年月が経っている場合もおいしく飲めるのか、気になる人もいるのでは?
ここでは、「年単位で自宅保管していた焼酎はおいしく飲める?」「数年前に開栓した焼酎は飲んでも大丈夫?」「開栓後は何年くらいもつの?」など、焼酎の賞味期限に関するよくある疑問に答えます。
未開封なら10年前の焼酎でもおいしく飲める!
未開封の焼酎で瓶詰めから10年が経過した焼酎も、適切な環境で保管されたものならおいしく飲むことができます。
瓶詰め後の焼酎は一般的に、熟成反応が進まないといわれていますが、時間の経過で酒質が落ち着いたり、味わいが微妙に変化したりする場合もあります。
昔ながらの単式蒸溜で造られる本格焼酎のなかには、瓶内での変化が顕著なものもあり、数カ月から数年の間にツンと鼻につくにおいが消えたり、油分が酸化し甘さが引き出されたり、まろやかさがプラスされたりすることがあります。ワインなどに比べるとその変化はゆるやかで、焼酎の個性や出来栄え、瓶詰め前の熟成度合いなどによって変化の方向性は異なりますが、時間の経過次第では、熟成香と呼ばれる香りが現れることも。
ただし、焼酎を瓶内で熟成させるためには、適切な環境下で保管することが大前提。熟成反応が起きたとしても、新しいころに比べて品質が向上するとは限りません。

shige hattori / PIXTA(ピクスタ)
開封後5年経った焼酎が飲めるかどうかは保存状態次第
焼酎はアルコール度数が比較的高く、腐敗の原因となる菌が繁殖しにくいことから、開封後(開栓後)も腐ることはないといわれています。キャップがしっかり閉まった状態で冷暗所に適切に保存されていれば開封後5年経った焼酎でも基本的には飲めますが、腐らないとはいえ一度空気に触れてしまうと、未開封のときに比べて香りや風味が変化しやすくなります。栓がしっかり閉まっていなかった場合は、アルコールが揮発している可能性も。
開栓後の焼酎がおいしく飲めるかどうかは、保存状態次第。造り手が想定し得ない環境で保存した場合は、品質が劣化し、香味が損なわれてしまうこともあります。
酒造メーカーのなかには、風味が変化する前に飲んでほしいという想いから、瓶は開封後約2年、紙パックやペットボトルは開封後約1年半以内に飲みきるよう推奨しているケースもあります。開封後は適切な保存を心がけ、なるべく早めに飲みきることをおすすめします。

beeboys / Shutterstock.com
焼酎が劣化しているかどうかをチェックする方法
焼酎を劣悪な環境下で長期間保管・保存すると、「におい」「見た目」「味」などに変化が生じます。開封前なら飲める確率は高いかもしれませんが、「日当たりのよい部屋から古い焼酎が出てきた」などという場合は要注意。飲む前に、今もおいしく飲めるかどうかを以下の手順で確認しておきましょう。
(1)においをチェック
焼酎は空気に触れたり紫外線にさらされたりすると、酸化臭が発生します。さらに時間が経過すると、酸化した油を思わせる不快なにおいを放つことも。酸っぱいにおいやすえたにおいがしたときは、飲むのをやめましょう。
(2)見た目をチェック
次に、透明なグラスに注いで白い沈殿物が浮遊していないかどうかを確認します。飲んでも健康を害するわけではありませんが、口あたりや味わいに影響をおよぼします。料理酒に使ったり、唐辛子を加えて防虫剤として活用するなど、ほかの使い道を考えましょう。
(3)味をチェック
においと見た目に問題がなければ、味を確認します。少量を口に含み、お酢のような味がしたら、飲むのをあきらめましょう。
焼酎の適切な保管・保存方法は?

VTT Studio / Shutterstock.com
賞味期限がない焼酎は、適切に保管・保存することで、長期間品質を保つことができます。ここからは、焼酎の保管・保存に適した条件をみていきます。
焼酎の品質を左右する3つの要素
焼酎の品質劣化のおもな原因は、紫外線と高温多湿な環境。開封後の焼酎なら、におい移りも大敵です。それぞれ詳しくみていきましょう。
【紫外線】
紫外線を浴びた焼酎は、油臭と呼ばれる劣化臭が発生する可能性があります。直射日光を避けるのはもちろんですが、蛍光灯や一部のLED照明が発する紫外線にさらされないよう工夫が必要です。
【高温多湿】
気温が20度を超える場所に焼酎を保管・保存すると、劣化を招くおそれがあります。逆に、10度以下の低温下に長時間保管すると、旨味成分が凝固してオリ(澱)が生じる可能性があります。
【におい移り】
食べ物に限らず香りの強いものの近くに置いておくと、においが移り、焼酎のよい香りが損なわれてしまうおそれがあります。
焼酎を保管・保存する際は、品質を左右するこれらの要素を遠ざけることを意識しなければなりません。

akiyoko / PIXTA(ピクスタ)
焼酎の保管・保存におすすめの場所と注意点
焼酎の保管・保存に適しているのは冷暗所。直射日光が当たる窓辺や熱を受けやすいキッチンは避け、常温より温度が低く、かつ温度変化の少ない場所を選びましょう。おすすめは床下収納や押し入れです。
冷暗所というと冷蔵庫を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、前述したように、焼酎は冷やしすぎるとオリを生じる可能性があるので、12〜16度程度の温度帯を保てる場所を選ぶのがおすすめです。
扉の開け閉めで照明器具が発する紫外線を受けるおそれがある場合は、木箱やセロファン、新聞紙などで焼酎の瓶を覆っておくのもひとつの手。紫外線を発生させない白熱球やLED照明に換えてもよいかもしれません。
開封後の焼酎を保存する際は、においの強いものを遠ざけるのはもちろんですが、まずはキャップをしっかり閉め、ボトルとキャップの間にすき間があるようなら、ラップをかぶせて輪ゴムで密封してしまいましょう。
焼酎に賞味期限はありませんが、時間が経って品質が劣化してしまった場合は飲むのをあきらめるのが賢明です。捨てるのはもったいないという場合は、家庭菜園用の防虫剤(防虫スプレー)という使い道もあります。唐辛子を数本加えて1週間ほど寝かせ、300倍程度に希釈するだけと作り方はかんたん。霧吹きに移して、庭や家庭菜園の害虫駆除に役立ててみてください。