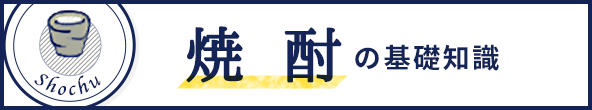山形の焼酎【きらら:小屋酒造】豪雪地帯の老舗蔵が造る本格焼酎

「きらら」は、山形県の老舗蔵、小屋酒造の焼酎銘柄です。雪深い環境で400年以上にもわたって酒造りを続けてきた小屋酒造は「花羽陽(はなうよう)」などの日本酒銘柄で知られています。日本酒造りでの工程で得られる酒粕を原料とした「きらら」の魅力を紹介します。
- 更新日:
「きらら」の蔵元、小屋酒造は400年以上続く老舗蔵

「きらら」は自然に恵まれた地の蔵で造られる
「きらら」は、山形県のほぼ中央に位置する最上郡大蔵村の蔵元、小屋酒造の焼酎ブランドです。
蔵が建つ大蔵村は、南西に出羽三山(でわさんざん)のひとつ月山(がっさん)を望み、山形県の母なる川・最上川(もがみがわ)やその支流が流れる自然豊かな地。今から1,200年以上も前に発見されたという肘折(ひじおり)温泉や、農林水産省選定の日本の棚田百選のひとつ「「四ヶ村(しかむら)の棚田」などの名所もあります。
大蔵村は国内有数の豪雪地帯としても知られています。冬ともなれば雪に囲まれ、酒造に適した低温環境が作り出され、雪解け水にも恵まれたこの地で、小屋酒造は酒造りを続けてきました。
「きらら」の蔵元、小屋酒造の歩み
「きらら」の蔵元、小屋酒造を営む小屋家は、福井の廻船問屋をルーツとする家柄です。山形に移ってからも、最上川を利用し人や荷を舟で運ぶ舟運(しゅううん)に深く関わり、庄屋や問屋、諸大名の本陣などの役割も担ってきました。
酒造業を始めたのは、今から400年以上さかのぼる文禄2年(1593年)のこと。豊臣秀吉が権勢を振るっていた時代です。代表銘柄として今も醸し続ける日本酒「花羽陽(はなうよう)」は、当時から神事や慶事には欠かせない酒として、参勤交代で本陣を訪れる諸大名をはじめ、霊峰・月山の参詣客や肘折温泉の観光客にも愛飲されてきました。
現在は「花羽陽」に加え、「最上川」という日本酒銘柄も造っています。焼酎「きらら」とともにぜひ味わってみてくださいね。
「きらら」は蔵元のこだわりから生まれる本格焼酎

tagu/ Shutterstock.com
「きらら」をはじめとする本格焼酎とは
「きらら」は、米と清酒粕を原料とした本格焼酎です。「本格焼酎」と表示するには、省令で定められた以下の条件を満たす必要があります。
(1)ほかの蒸留酒に該当しない、単式蒸溜機で蒸溜したアルコール分45度以下のもの=単式蒸溜焼酎。
(2)「穀類」「芋類」「清酒かす」「砂糖(政令で定めるものに限る)」、または政令で定める物品を原料とし麹を使用する。
(3)水以外の添加物を一切使わない。
原料そのままの風味を活かした単式蒸溜焼酎は、かつての酒税法で「乙類」と分類されたことで、連続式蒸溜機で大量生産される「甲類」の焼酎より品質が劣ると誤解されてきました。そこで新たに生まれた呼称が「本格焼酎」です。
「きらら」の蔵元のこだわりの酒造り
「きらら」の蔵元、小屋酒造がめざすのは、さらりと飲めて、料理とともにたのしめる、最後まで飲み飽きず何杯でも猪口が進む酒造り。
そこで、酒造りに欠かせない麹菌や酵母といった微生物と真剣に向き合うことが大切との考えから、機械化や合理化には消極的です。蔵全体に目が届くような環境を整えつつ、できる限り人の手による酒造りにこだわり続けています。
原料米には、酒造好適米「出羽燦々(でわさんさん)」や食用米「つや姫」など地元山形産米を中心に、銘柄に合わせて厳選。仕込み水には、豪雪地帯の大蔵村ならではの良質な雪解け水を用いています。
さらに、蔵人もみな山形出身と、徹底して山形産にこだわった「きらら」は、まさに山形の地が育んだ、山形の焼酎といえるでしょう。
「きらら」は香味に優れた本格焼酎ブランド

kai keisuke / Shutterstock.com
「きらら」の味わいの特徴
「きらら」が原料とするのは、日本酒の原料でもある米と、日本酒の製造過程で醪(もろみ)を搾ったあとに残る酒粕です。
このため、「きらら」は焼酎でありながら、日本酒を思わせる飲み口をたのしめます。料理との相性もよく、とりわけ和食によく合います。蔵元が「造り酒屋の焼酎」と銘打つのも納得できるというものです。
きめ細かで飲み飽きしない味わいと、華やかな香りをもつ本格焼酎「きらら」は、山形名物のそばなどと一緒に、ロックや水割り、お湯割りなどでたのしむのがオススメです。
「きらら」ブランドのラインナップ紹介
本格焼酎「きらら」ブランドには、定番となる「きらら」に加えて、2種類のバリエーションがラインナップされています。さらに、小屋酒造サイトには掲載されていないものの、大蔵村と同じ最上地域にある金山町の農業組合法人の依頼で製造した「つや極み焼酎金山」も製造しています。
【きららフルーティー】
400年以上にわたり培ってきた酒造りの伝統と卓越した技術から生まれた、ほのかな甘味と気品のある香りを特徴とする本格焼酎です。果実を思わせる香りが蔵中に広がったことから「きららフルーティー」と命名されました。
【きらら樽貯蔵】
よく磨かれた米と酒粕を雪国の清冽な水で仕込み、単式蒸溜によって生み出された本格焼酎を、ヨーロッパ製の木樽で熟成させた逸品。豊潤な香りとまろやかな味わいが心ゆくまでたのしめます。
【つや極み焼酎金山】
山形県金山町の農事組合法人いずえむが小屋酒造に製造を依頼して生まれた焼酎です。金山町産の食用米「つや姫」を原料に、吟醸造りの技術を取り入れて低温発酵させることで引き出したフルーティーな香りがたのしめます。
豪雪地帯の蔵元が厳選した原料からていねいに造る本格焼酎「きらら」シリーズ。機会があれば、それぞれの味わいの違いをたのしんでみてください。
製造元:株式会社小屋酒造
公式サイトはこちら